名前:
平野さん
業種・職種:
業種/不動産運営管理
職種/情報システム

急速な外部環境の変化・進化により、企業はDXの重要性は理解しつつも、一方で、多くの企業はDXの取組みに遅れをとっており、その大きな要因のひとつが、DXを推進できる人材が不足していることが挙げられます。
そこで、本プログラムは産学連携により、最新のDX理論と実践的なスキルを融合させ、企業の変革を牽引する次世代リーダーを育成します。大学の知見と企業の実践知を結集し、即戦力となるDX人材を輩出します。

経済産業省のデジタルスキル標準をベースにしたカリキュラムにより、誰でも学ぶべきDXリテラシーからリーダーに求められる推進スキルの基礎までを網羅的に学習。理論と実践のバランスが取れた内容で、確実なスキルアップを実現します。
必須授業でビジネス変革を推進できる人材育成を目的とした内容と、選択授業にて求められる基礎的な共通スキルも学べる構成に。

必須授業
全ての授業を受講してください

DXに求められる思考術
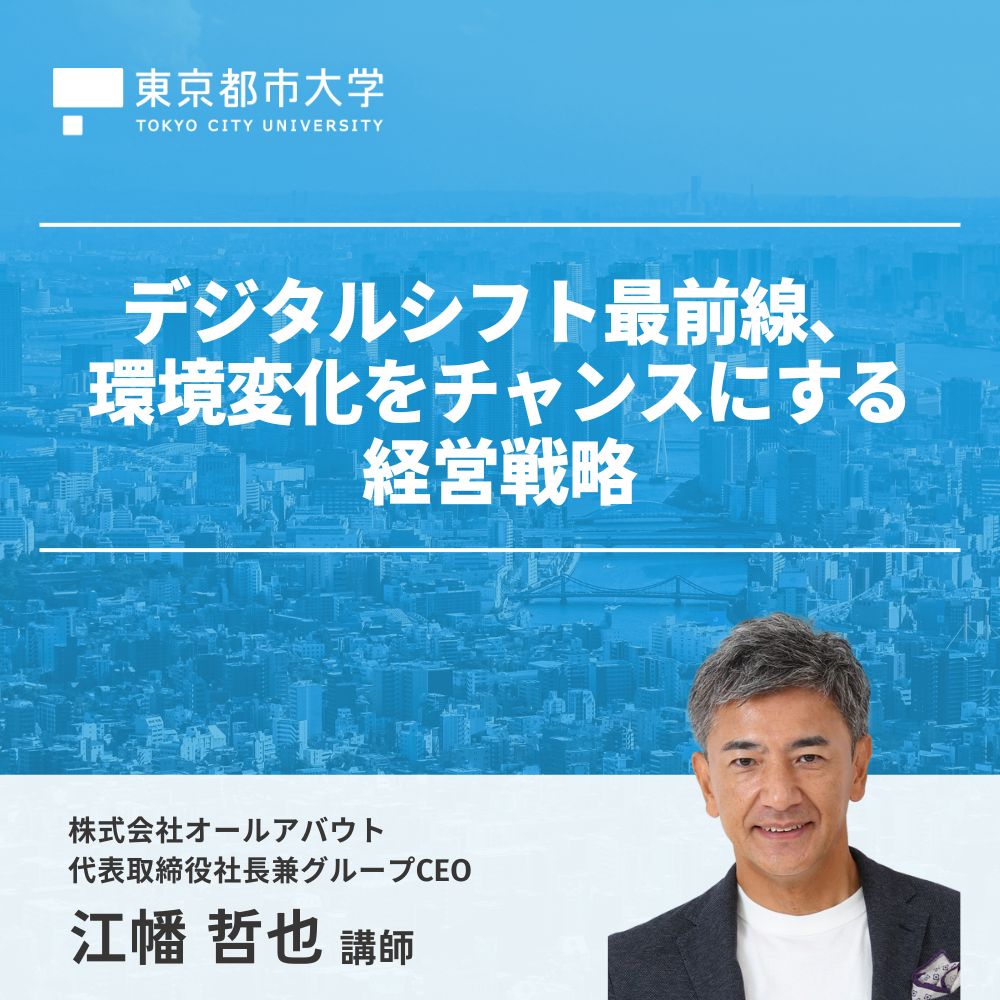
デジタルシフト最前線、環境変化をチャンスにする経営戦略

DXはどのように顧客価値を創造するか - 製品戦略の観点から

経営戦略としてのDX

ブランド価値を高める共創マーケティング

上場企業・スタートアップにおける事業の創り方

ビジネス現場から学ぶデータ活用術

「DX実践におけるビジネスアーキテクトの重要性」及びコースガイダンス・オリエンテーション

| 講義 | DXに求められる思考術 |
|---|---|
| 開講日 | 9月5日(金)19:00~20:30 |
| 講師名 | 鈴木 康弘 講師 |

株式会社デジタルシフトウェーブ 代表取締役社長 |
|
| 1987年 | 富士通に入社。SEとしてシステム開発・顧客サポートに従事。 |
|---|---|
| 1996年 | ソフトバンクに移り、営業、新規事業企画に携わる。 |
| 1999年 | ネット書籍販売会社、イー・ショッピング・ブックス(現セブンネットショッピング)を設立し、代表取締役社長就任。 |
| 2006年 | セブン&アイHLDGS.グループ傘下に入る。 |
| 2014年 | セブン&アイHLDGS.執行役員CIO就任。グループオムニチャネル戦略のリーダーを務める。 |
| 2015年 | 同社取締役執行役員CIO就任。2016年同社を退社。 |
| 2017年 | デジタルシフトウェーブを設立。同社代表取締役社長に就任。他に日本オムニチャネル協会 会長、SBIホールディングス社外役員、東京都市大学特任教授を兼任。 |
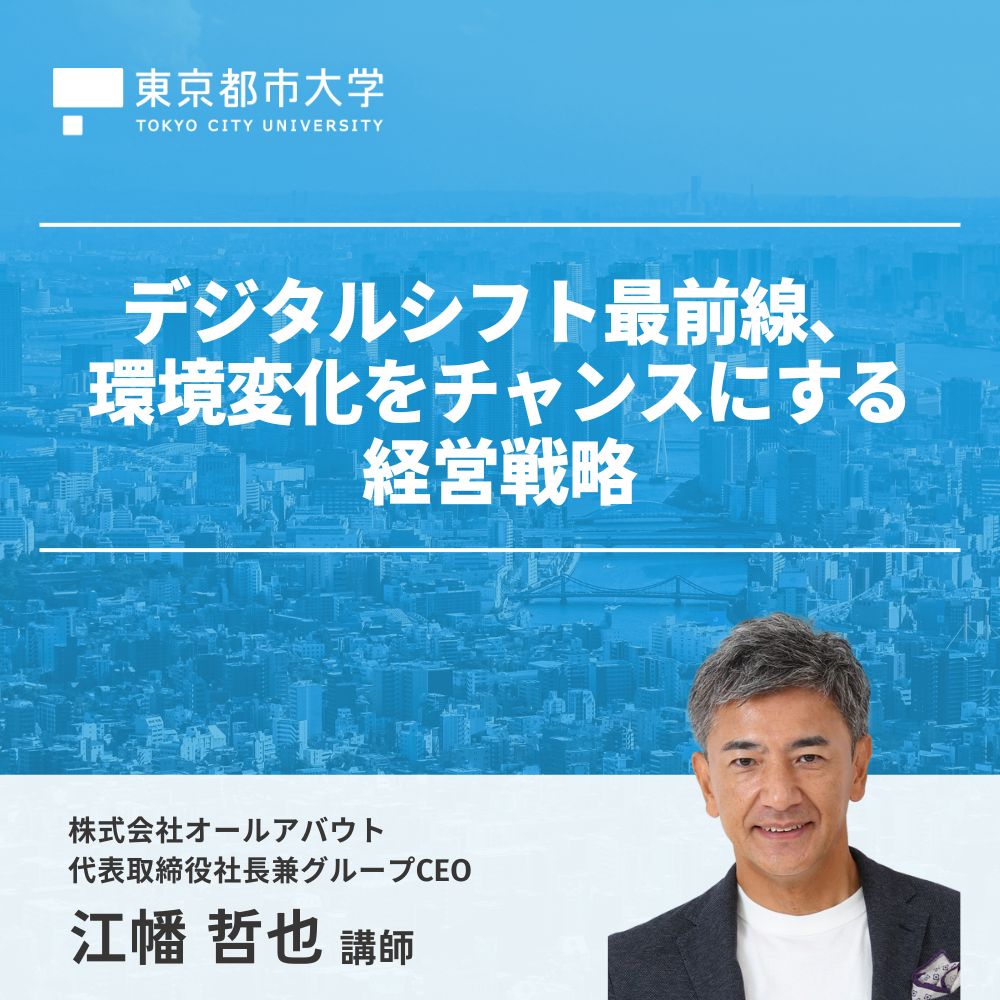
| 講義 | デジタルシフト最前線、環境変化をチャンスにする経営戦略 |
|---|---|
| 開講日 | 7月8日(火)19:00~20:30 |
| 講師名 | 江幡 哲也 講師 |

株式会社オールアバウト 代表取締役社長兼グループCEO |
|
| 経歴 | 武蔵工業大学(現 東京都市大学)電気電子工学科卒業。 |
|---|---|
| 1987年 | 株式会社リクルート入社。エンジニアとしてキャリアをスタートし、その後数多くの事業を立ち上げる。 |
| 1996年 | 自ら立ち上げたキーマンズネットにおいては、14個のネット関連特許を取得し、高い評価を得る。 |
| 1998年度 | 全国優秀システム賞受賞。 |
| 2000年 | 6月に株式会社リクルート・アバウトドットコム・ジャパンを設立。代表取締役社長兼CEOに就任。 |
| 2004年 | 7月に株式会社オールアバウトに社名を変更。 |
| 2005年 | 9月にJASDAQ上場を遂げる。 |
| 2006年 | 講談社から「アスピレーション経営の時代」を発刊。専門家ネットワークを基盤に世の中の「情報流・商流・製造流」の不条理・不合理に対してイノベーションを起こし、"個人を豊かに、社会を元気に"することを目指す。 |
| 2022年度 | 東京都市大学大学院 総合理工学研究科 客員教授 就任。 |

| 講義 | DXはどのように顧客価値を創造するか - 製品戦略の観点から |
|---|---|
| 開講日 | 7月11日(金)19:00~20:30 |
| 講師名 | 挽野 元 講師 |

アイロボットジャパン合同会社 代表執行役員社長 |
|
| 1992年 | 横河ヒューレット・パッカード (現 日本ヒューレット・パッカード) 株式会社入社。 パーソナルコンピュータの市場開発や製品を企画。 |
|---|---|
| 1996年 | HPフランスにてグローバル市場に向けた製品マーケティング・マネジメントの担当を経て、1999年帰国。 |
| 2000年 | 日本市場でのノートブックビジネスの立ち上げを行い、アジア太平洋地域に責任範囲を広げる。 |
| 2002年 | Hewlett-PackardとCompaq の合併後、日本市場でのモバイルビジネスの責任者として従事。 |
| 2006年 | 同社 執行役員、米国Hewlett-Packard Vice Presidentに就任。イメージング・プリンティングビジネス事業統括として、家庭内印刷向け、企業内印刷向け、印刷事業者向け印刷のビジネスに従事。 |
| 2010年 | 同社取締役に就任。 |
| 2017年 | アイロボットジャパン設立と同時に、代表執行役員社長に就任。 |
| 2018年 | 中国、韓国、豪州、東南アジアなどのアジア太平洋地域全体を統括するiRobot Corporation Vice President Asia Pacificも兼任し、現在に至る。 |

| 講義 | 経営戦略としてのDX |
|---|---|
| 開講日 | 7月31日(木)19:00~20:30 |
| 講師名 | 磯村 康典 講師 |

株式会社トリドールホールディングス 執行役員 CIO 兼 CTO 神奈川県横浜市出身。 |
|
| 1993年 | 3月、武蔵工業大学工学部機械工学科卒業。 同年4月より富士通株式会社へ入社してシステムエンジニアとしてのキャリアを開始。 |
|---|---|
| 2000年 | ソフトバンク社へ入社し、後にセブンネットショッピングとなるネット通販事業の EC システム開発・運用責任者を務める。 |
| 2008 年 | 株式会社ガルフネット 執行役員へ就任し、飲食業向け IT システム開発責任者、アウトソーシングサービス運営責任者、営業責任者を歴任。 |
| 2012年 | Oakキャピタル株式会社 執行役員へ就任し、ハンズオンによる経営再建に従事。 |
| 2019 年 | 株式会社トリドールホールディング 執行役員 CIO へ着任。シェアードサービス子会社社長を兼務して業務改革を推進し、現職に至る。 |

| 講義 | ブランド価値を高める共創マーケティング |
|---|---|
| 開講日 | 7月10日(木)19:00~20:30 |
| 講師名 | 長田 新子 講師 |

| 会社名 | 一般社団法人渋谷未来デザイン |
|---|---|
| 役職 | 理事・事務局長 |
| 経歴 | AT&T、ノキアにて通信・企業システムの営業、マーケティング及び広報責任者を経て、2007年にレッドブル・ジャパンに入社。コミュニケーション統括責任者及びマーケティング本部長(CMO)として10年半、エナジードリンクのカテゴリー確立及びブランド・製品を市場に浸透させるべく従事し2017年に退社。 |

| 講義 | 上場企業・スタートアップにおける事業の創り方 |
|---|---|
| 開講日 | 7月17日(木)19:00~20:30 |
| 講師名 | 張本 貴雄 講師 |

| 会社名 | Free Standard株式会社 |
|---|---|
| 役職 | 代表取締役社長 |
| 2007年 | クルーズ入社。 |
| 2020年 | クルーズ取締役を退任。同年にFreeStandardを設立。 |

| 講義 | ビジネス現場から学ぶデータ活用術 |
|---|---|
| 開講日 | 7月19 日(土)10:00~11:30 |
| 講師名 | 見並 まり江 講師 |

| 会社名 | 株式会社Rejoui |
|---|---|
| 役職 | 取締役 |
| 2006年 | 株式会社ALBERT入社。 |
| 2016年 | 株式会社アイスタイル入社。 |
| 2019年 | 株式会社Rejoui 取締役就任。 |

| 講義 | 「DX実践におけるビジネスアーキテクトの重要性」及びコースガイダンス・オリエンテーション |
|---|---|
| 開講日 | 7月4日(金)19:00~20:30 |
| 講師名 | 川邉 雄司 講師 |

株式会社YKB 代表取取締役社長 |
|
| 2001年 | 武蔵工業大学 環境情報学部(1期生)卒業。 同年、株式会社マクニカ入社、半導体やネットワーク機器のフィールドセールスを担当。 |
|---|---|
| 2003年 | NSC吉本総合芸能学院入学(東京9期生)、卒業後は様々なアルバイトも経験。 |
| 2005年 | アップラン株式会社を創業、自治体向けにWebサイト管理システムを提供。 |
| 2007年 | ビジネスサーチテクノロジ株式会社へ転籍、サイト内検索サービスの企画・営業・事業開発を担当。 |
| 2014年 | SBI FinTech Solutions株式会社とのM&Aを機に、代表取締役就任。事業戦略の見直しや管理体制の強化を行い、赤字から黒字へ転換。 |
| 2020年 | 株式会社ジーニーへM&A。同日代表取締役辞任。 |
| 2021年 | 株式会社YKB創業、SaaS・新規事業支援やM&Aアドバイス等、コンサルティングやアクセラレーションを行う。 |
選択授業
以下から2つの授業を選択してください。
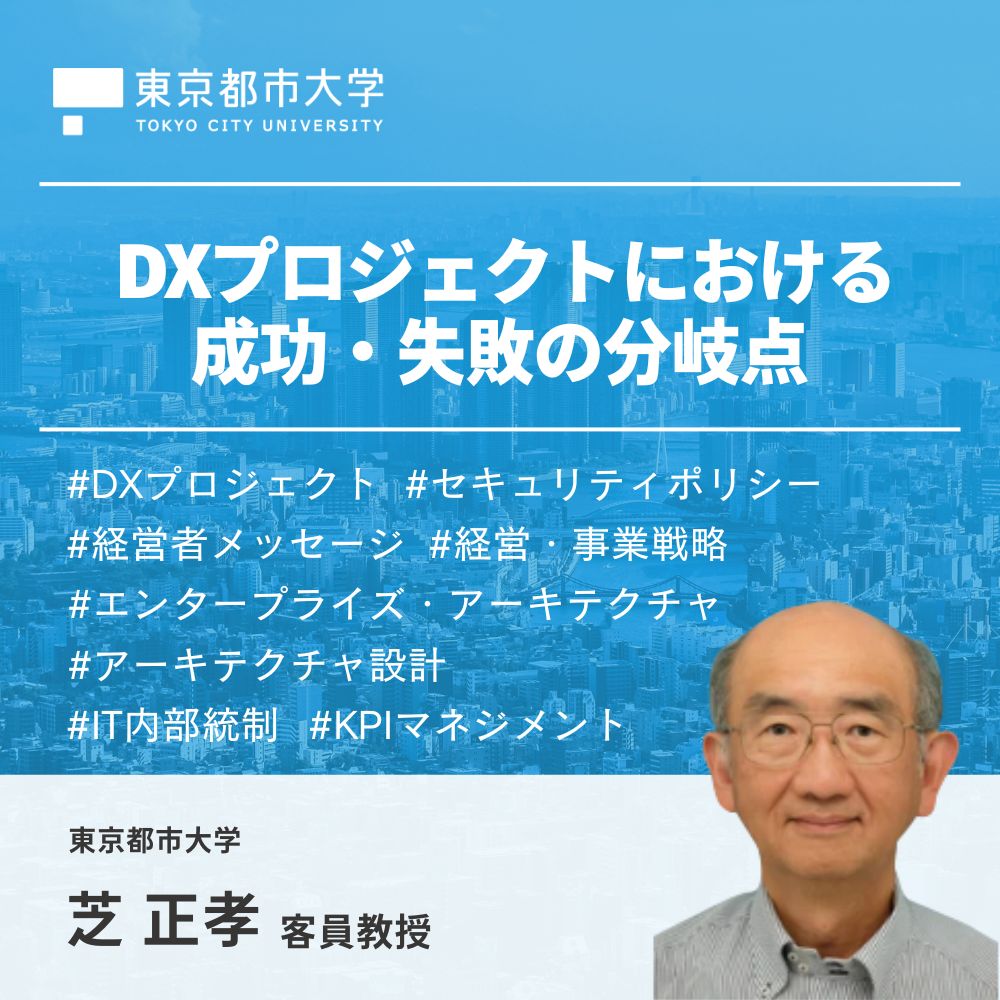
DXプロジェクトにおける成功・失敗の分岐点
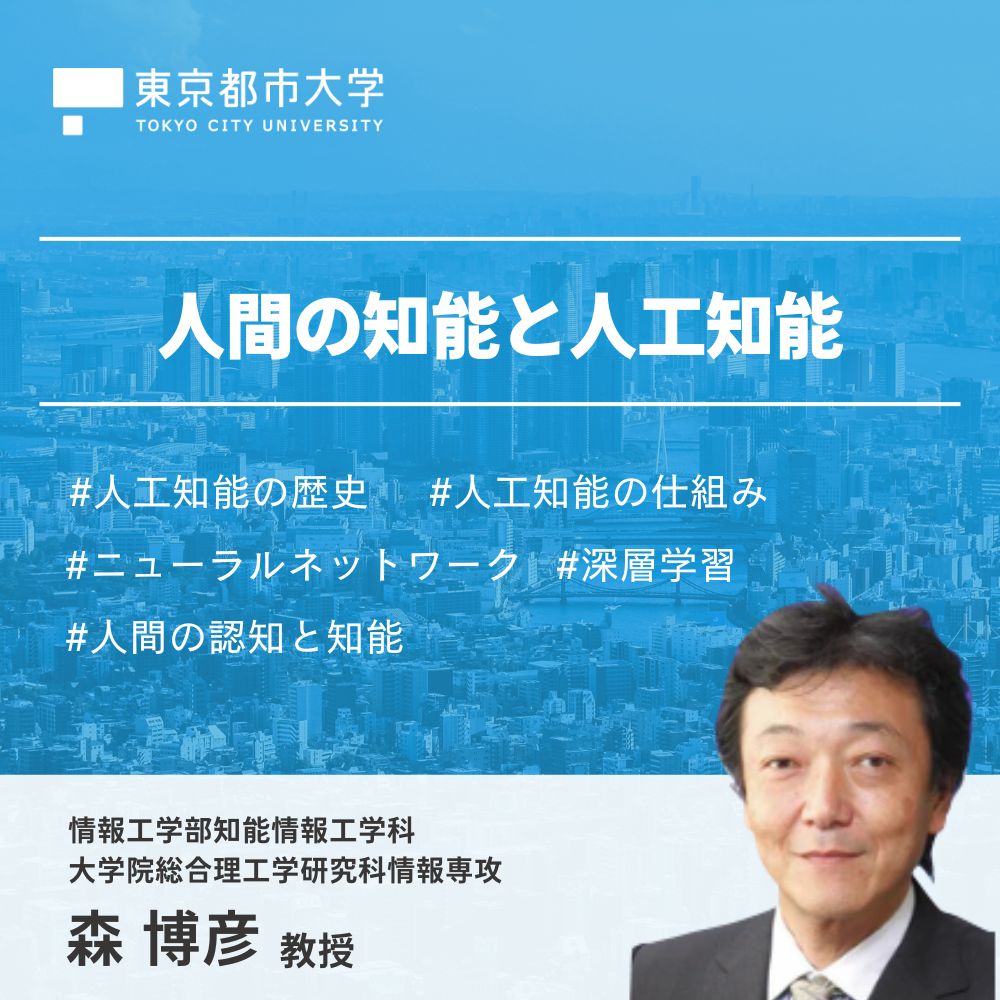
人間の知能と人工知能
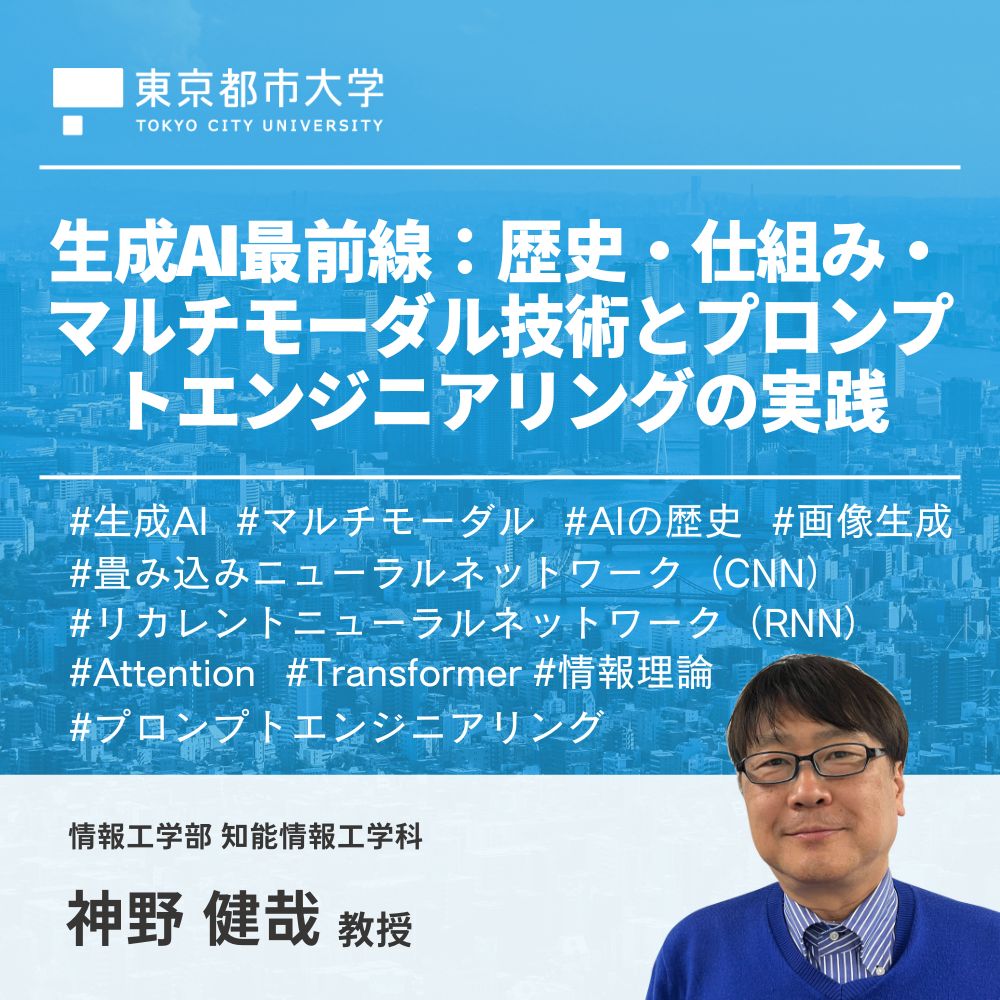
生成AI最前線:歴史・仕組み・マルチモーダル技術とプロンプトエンジニアリングの実践
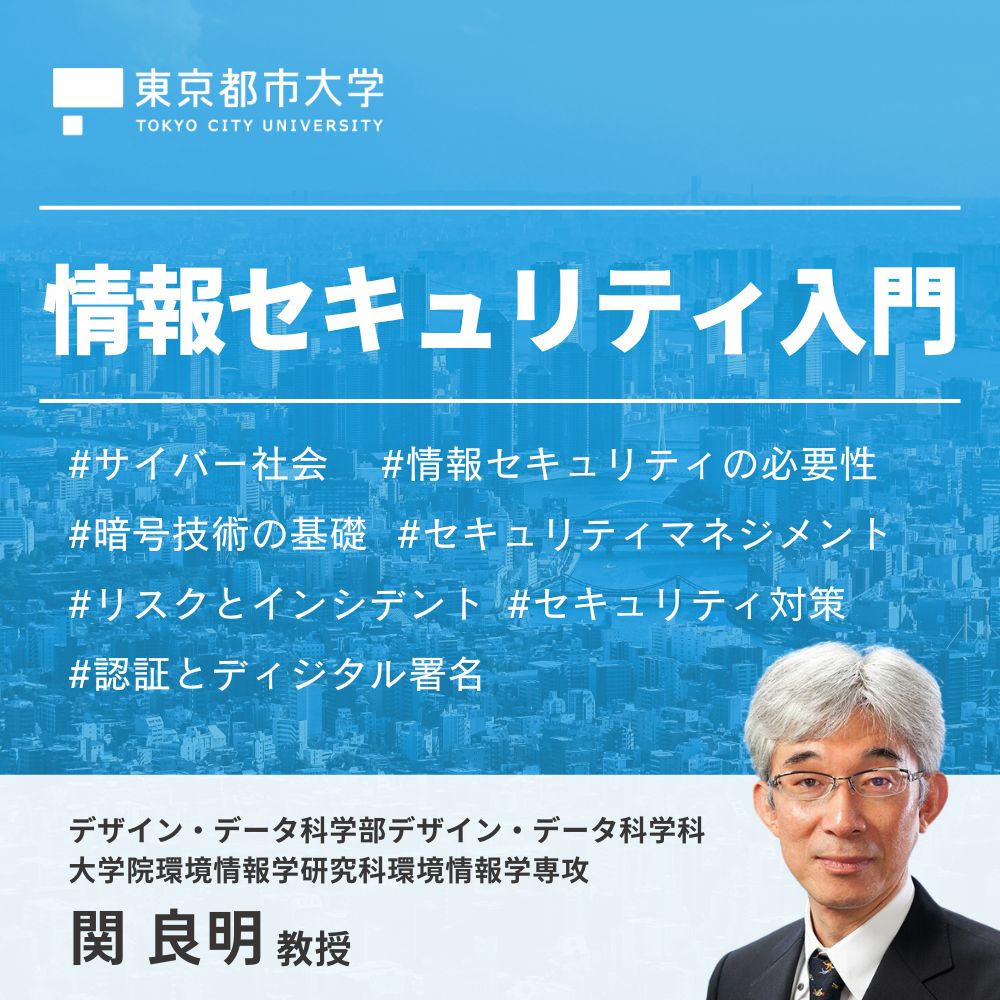
情報セキュリティ入門
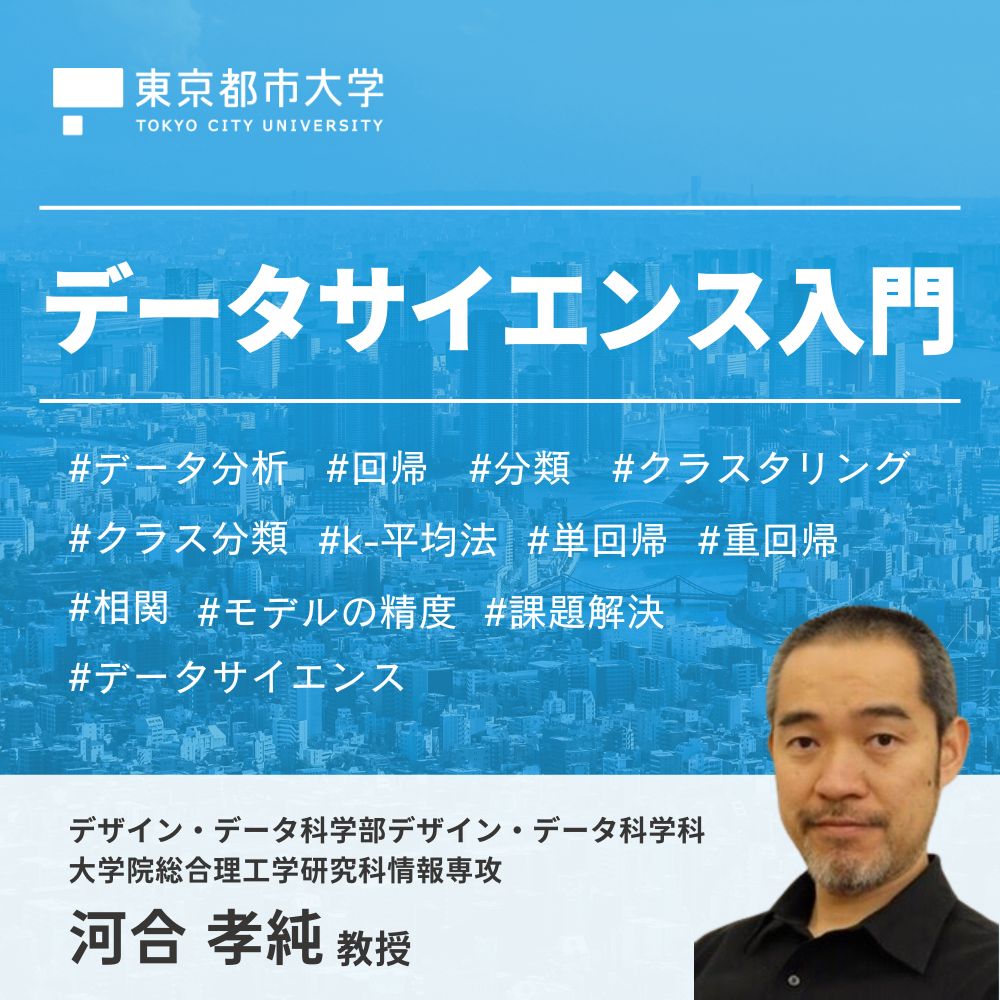
データサイエンス入門
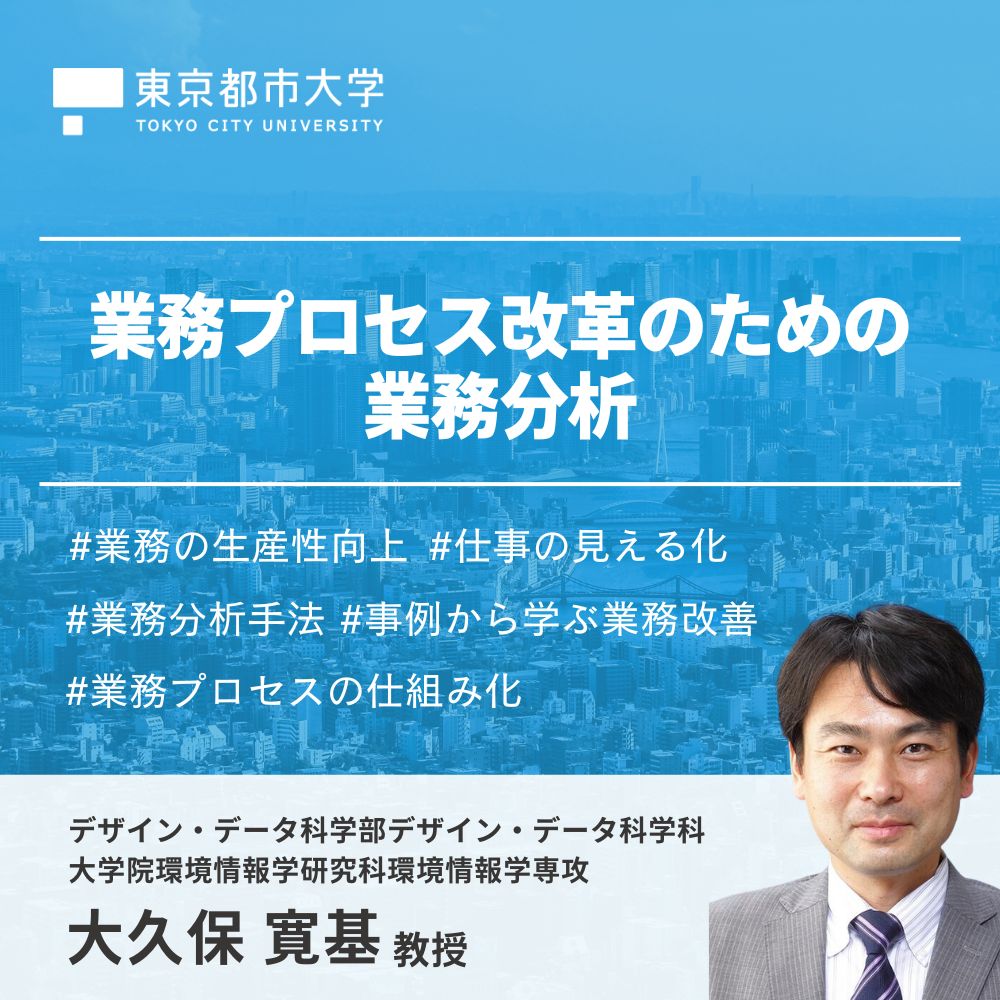
業務プロセス改革のための業務分析

ビジネスで活用する統計学入門
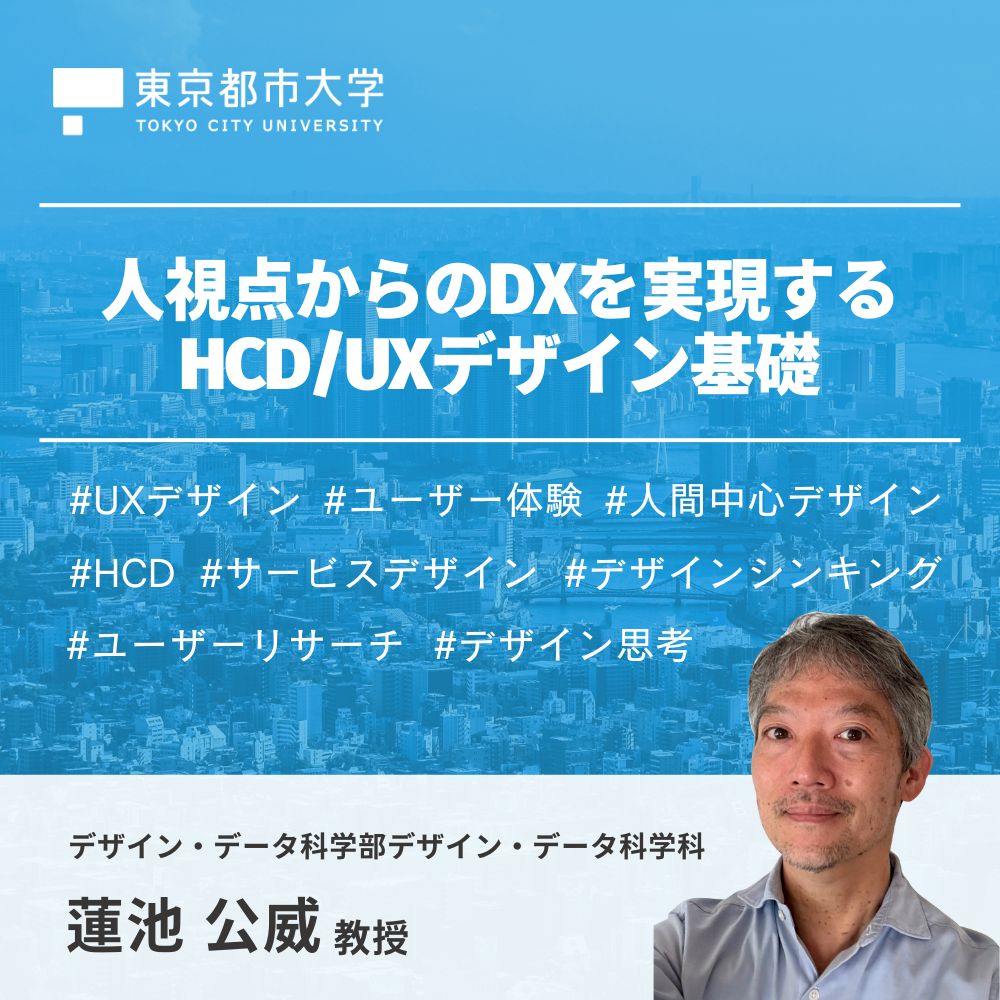
人視点からのDXを実現するHCD/UXデザイン基礎
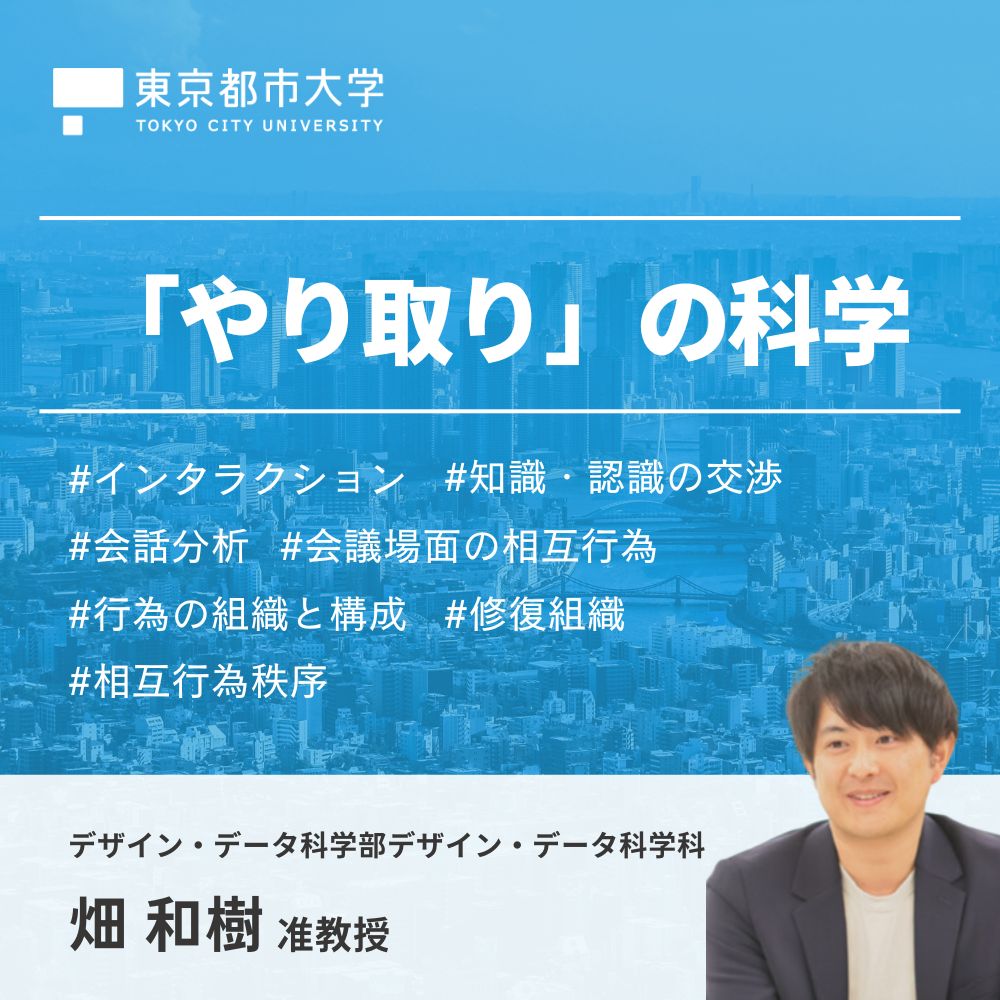
「やり取り」の科学
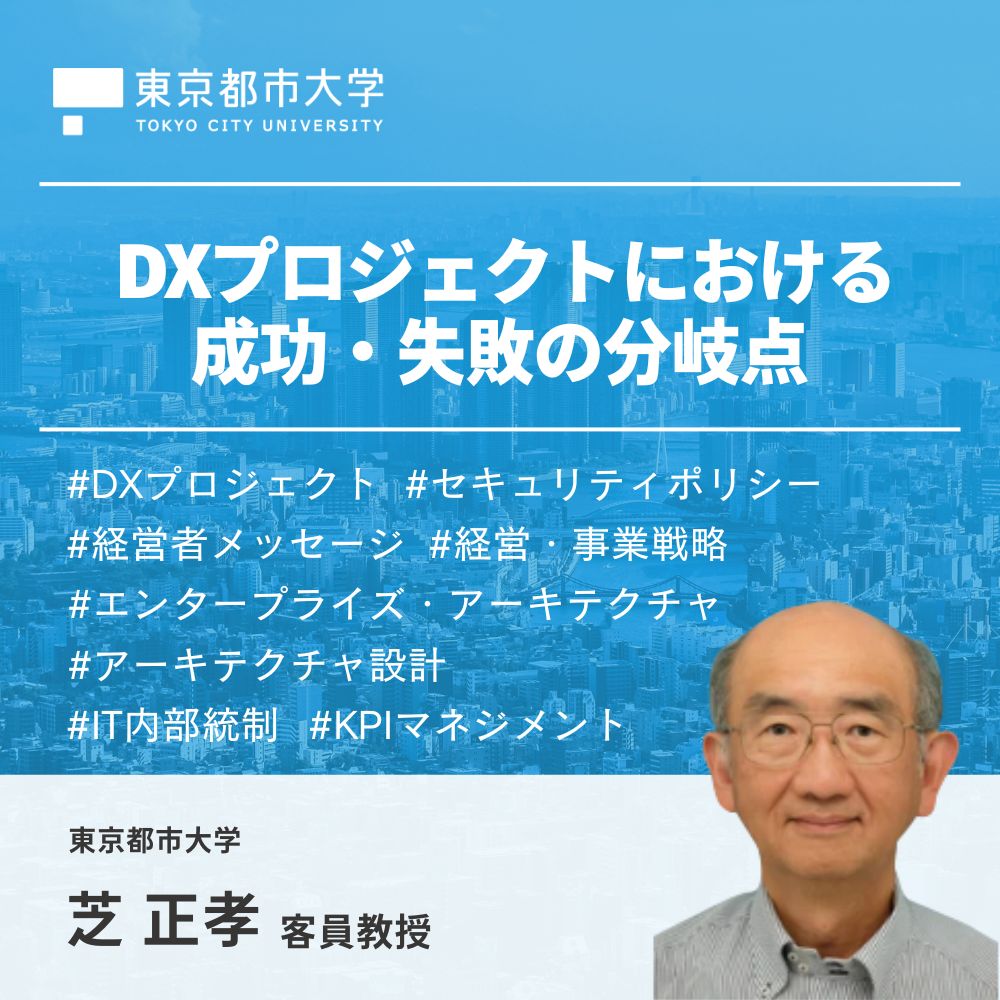
| 講義 | DXプロジェクトにおける成功・失敗の分岐点 |
|---|---|
| 開講日 | 1コマ目 |
| 講師名 | 芝 正孝 客員教授 |
| 前提知識 | 特になし |
| 事前準備 | Powerpoint、ZOOM(画面共有機能を使います)がインストールされたPC |
DXプロジェクトを推進する多くの方が、途中で大きな壁にぶち当たります。その壁を乗り越えてプロジェクトを成功に導くためにはどうすればいいのでしょうか?
理論を頭で理解することと、それを実行に移せることには大きなギャップがあります。泥臭いことや、直接関係のないことが、そのギャップを埋めるカギとなり、DXプロジェクトを成功に導くこともあります。
この講義では、身近な事例を基に4~5名でグループワークを行い、その結果を発表する中で、プロジェクトの成功・失敗を分ける重要ポイントを実感してもらいます。なお、講義に先立ち、グループワークをより密度の濃いものにするため、簡単な事前課題を出す予定です。

| 役職 | 東京都市大学 客員教授 |
|---|---|
| 1980年 | 東京大学大学院精密機械工学専攻修士課程を終え、日立製作所に入社。 |
| 2016年 | ビジネスコンサルタントとして独立。 |
| 2020年 | 東京都市大学 情報工学部知能情報工学科 特任教授 |
| 2025年 | 東京都市大学 客員教授 |
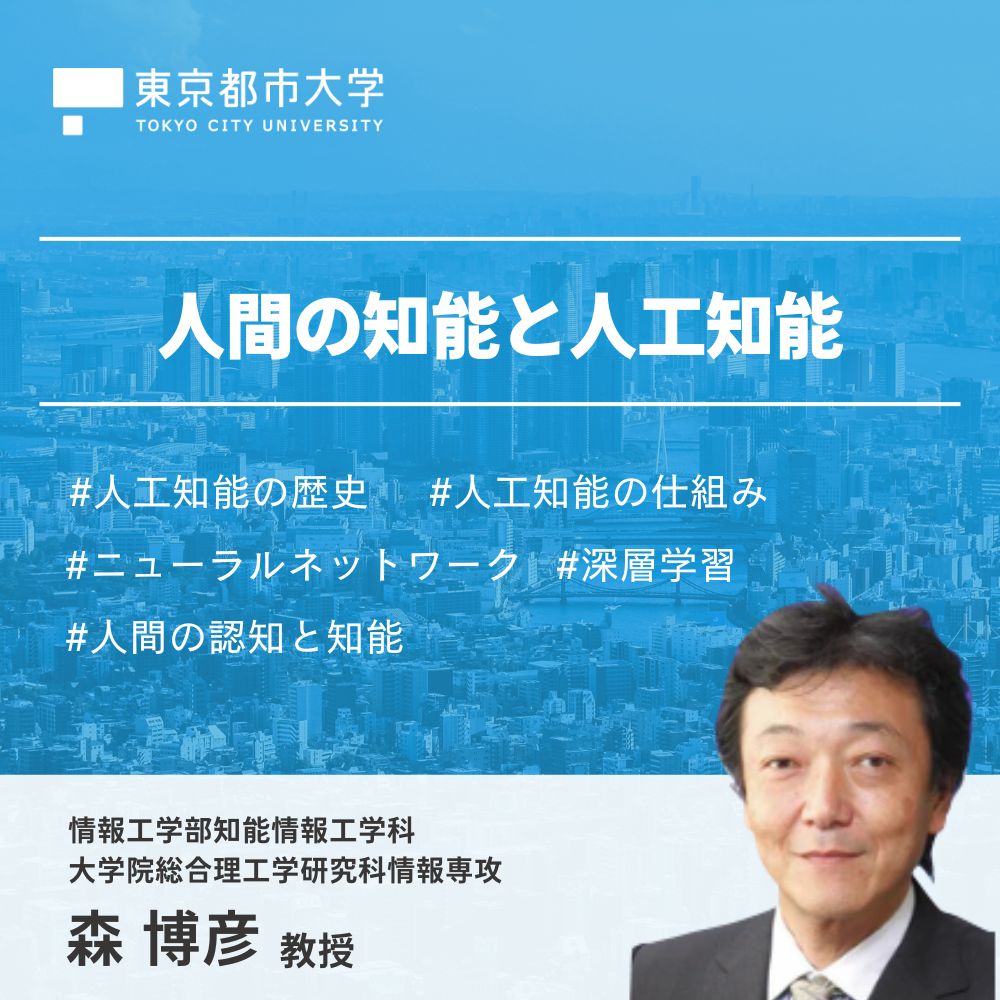
| 講義 | 人間の知能と人工知能 |
|---|---|
| 開講日 | 1コマ目 |
| 講師名 | 森 博彦 教授 |
| 前提知識 | 特になし |
| 事前準備 | PC |
本講義では人間の知能と人工知能がどのように違うのかについて理解し、人間と人工知能がどのように協調していくべきか考察することを最大の目的としている。そのために、人工知能の仕組みの基本を知る必要がある。まず最初に人工知能はどのような考え方のもとどのように発展したのか、人工知能の基本的な仕組みはどのようなものを理解しなければならない。本来、現代の人工知能は数学的理論に基づいているが、本講義ではできる限り数学が理解できなくても、そのイメージを伝えていきたいと考えている。そのうえで人間の知能、特に人工知能との違う部分についての解説をしていく。

| 役職 | 情報工学部長・知能情報工学科教授 |
|---|---|
| 1986年 | 慶應義塾大学理工学部管理工学科卒業 |
| 1991年 | 慶應義塾大学大学院理工学研究科管理工学専攻修了 |
| 1991年 | 武蔵工業大学 助手 |
| 1994年 | 武蔵工業大学 講師 |
| 1996~1997年 | トロント大学 計算機科学科 客員助教授 |
| 1998年 | 武蔵工業大学 助教授 |
| 2003年 | 武蔵工業大学 教授 |
| 2017年 | HCI International, Human Interface and Management of Information Area Chair(現在に至る) |
| 2024年 | 東京都市大学情報工学部長(現在に至る) |
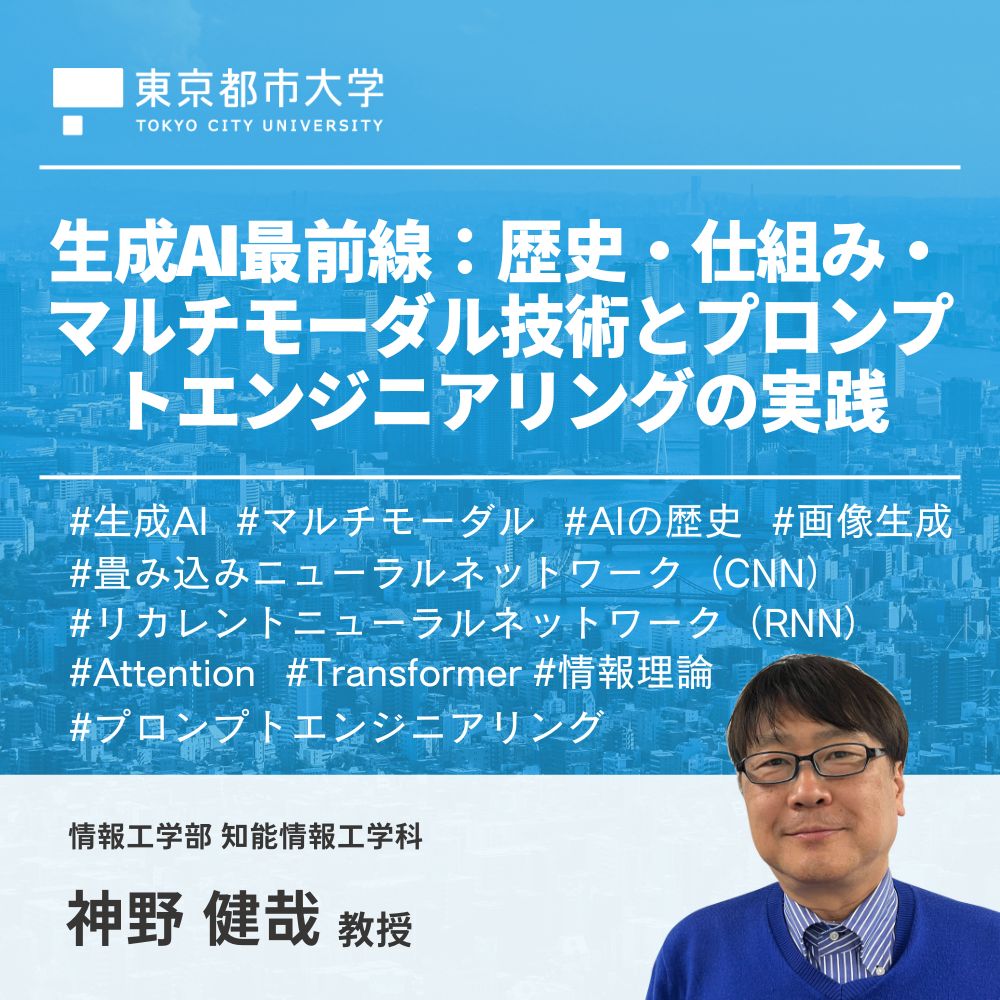
| 講義 | 生成AI最前線:歴史・仕組み・マルチモーダル技術とプロンプトエンジニアリングの実践 |
|---|---|
| 開講日 | 1コマ目 |
| 講師名 | 神野 健哉 教授 |
| 前提知識 | 特になし |
| 事前準備 | PC |
本講義シリーズは、生成AIの誕生から最新技術の応用まで、全3回で体系的に学ぶプログラムです。第1回では、初期のAI研究やルールベースシステムからニューラルネットワークの進化、そして生成AIの登場に至る歴史と技術革新を概観します。第2回では、CNNをはじめとするディープラーニングの原理を通じた画像処理や特徴抽出、複数のデータ形式を統合するマルチモーダルAIの仕組みと応用事例を紹介します。第3回では、生成AIやマルチモーダルAIの性能を引き出すためのプロンプトエンジニアリングの基礎から実践手法、具体的なケーススタディを通じ、今後の展望に迫ります。

| 所属 | 情報工学部 知能情報工学科 |
|---|---|
| 役職 | 教授 |
| 1996年 | 法政大学大学院工学研究科博士後期課程修了。 |
| 2018年 | 東京都市大学知識工学部情報通信工学科 |
| 2019年 | 東京都市大学情報工学部知能情報工学科教授、現在に至る。 |
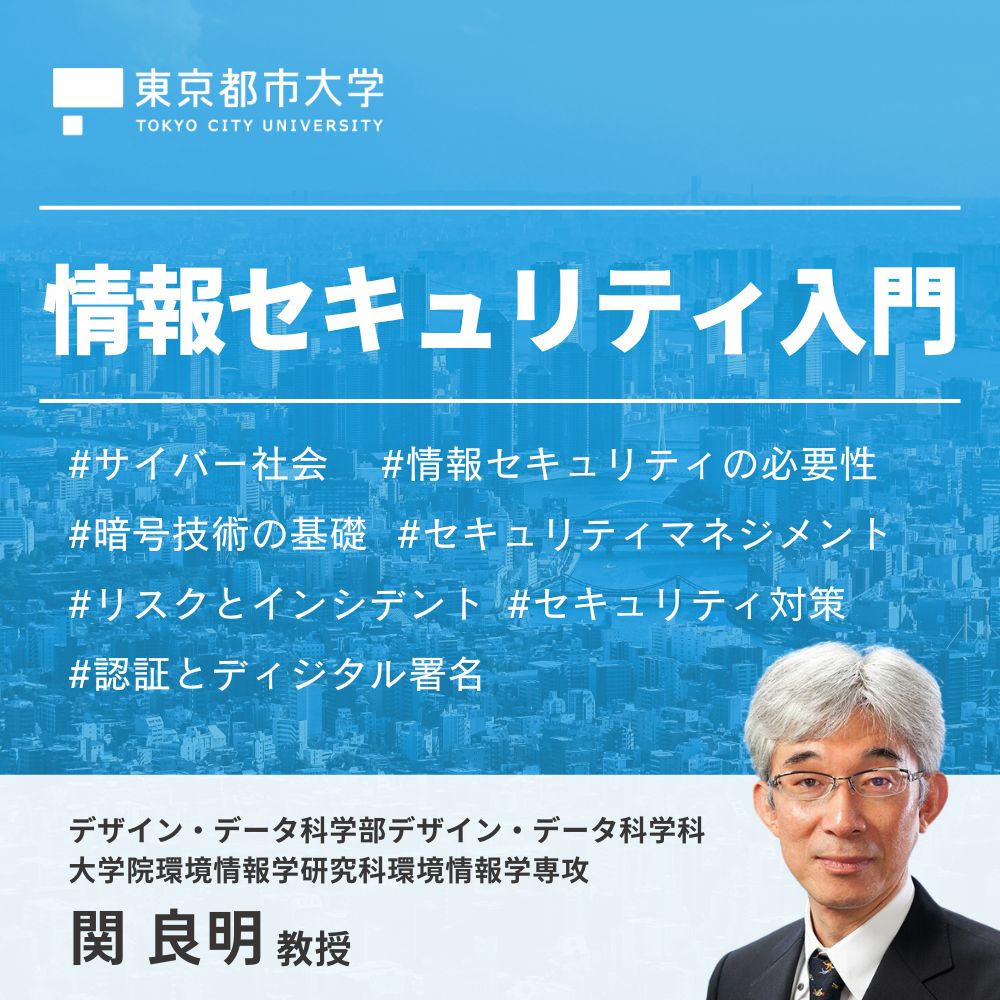
| 講義 | 情報セキュリティ入門 |
|---|---|
| 開講日 | 1コマ目 |
| 講師名 | 関 良明 教授 |
| 前提知識 | 特になし |
| 事前準備 | PC |
情報セキュリティは、私たちの身近なテーマであり、個人でも企業でも組織でも関心が高いと思います。身近なテーマではありますが、パソコンやネットワークの仕組み、世界的なルール、事件が起きた際の対応など、専門的知識が必要となります。
情報セキュリティ入門では、主に非IT系や非ビジネス系のリーダー層および中堅社員を対象に情報セキュリティの基本的な考え方を概観します。
講義内容は情報セキュリティの社会的背景、その役割と基本技術、暗号技術の基礎、認証とディジタル署名、リスクとセキュリティ対策、社会の一員としての情報セキュリティを予定しています。
専門的な知識がなくても問題意識をお持ちなら受講いただけます。

東京都市大学 |
|
| 1985年 | 東北大学工学部通信工学科 卒業。 |
|---|---|
| 2001年 | 博士(情報科学)東北大学 取得。 |
| 2014年 | 東京都市大学 メディア情報学部 情報システム学科教授。 |
| 2018年 | メディア情報学部長。 |
| 2021年 | 副学長(キャンパス連携担当)。 |
| 2023年 | デザイン・データ科学部長。 |
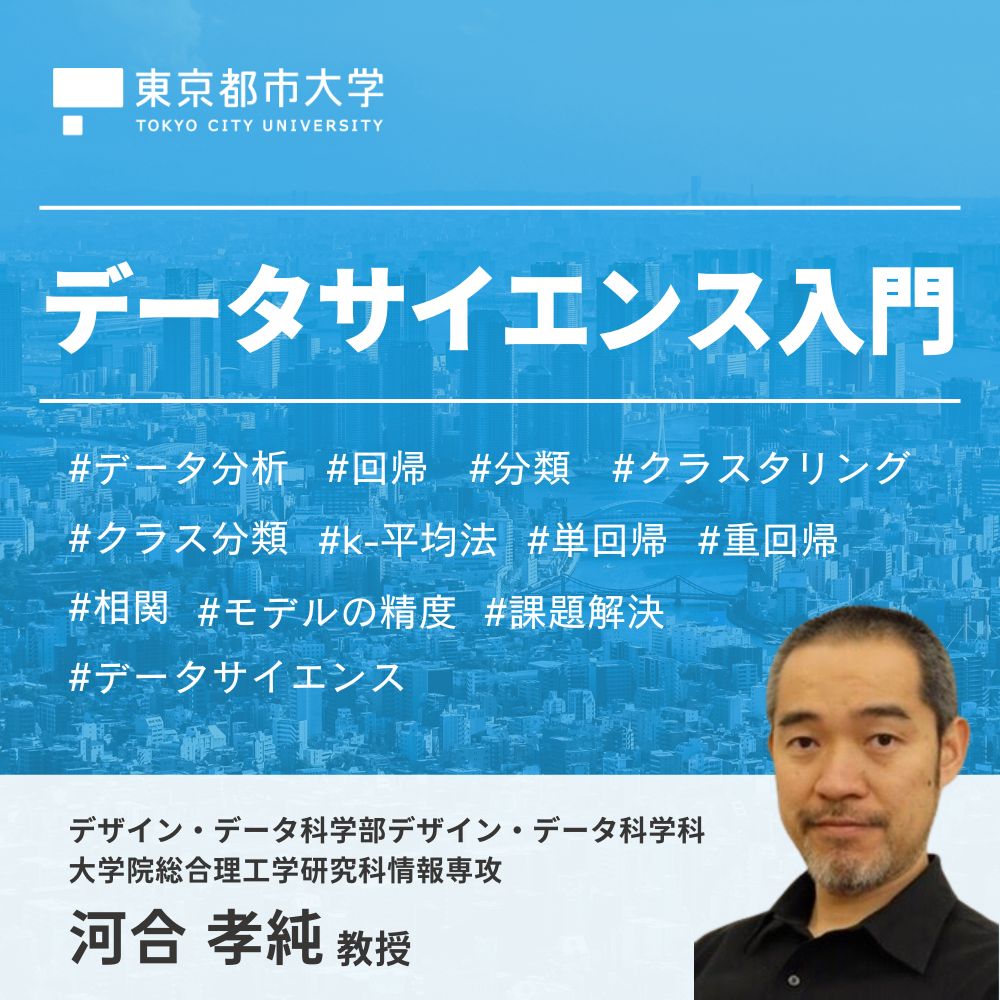
| 講義 | データサイエンス入門 |
|---|---|
| 開講日 | 1コマ目 |
| 講師名 | 河合 孝純 教授 |
| 前提知識 | 特に前提知識は必要ありませんが、多少、数式や数学的な考え方が出てくるので、数学に対して忌避感があると難しいかも知れません。 |
| 事前準備 | google |
「分類」や「回帰」などのデータ分析の基礎となる技術について、直感的な理解とともにデータサイエンスによる課題解決の方法について学びます。具体的にはクラスタリングの方法として、k-平均法、クラス分類の方法として、線形判別分析、さらに、単回帰分析、重回帰分析の方法について説明し、実際に表計算ソフトなどを使って演習を行います。また、データサイエンスによる課題解決について、課題の発見から解決までの流れを具体的に検討し、グループで議論していただく予定です。

| 1995年 | 3月 東京理科大学理学部物理学科 卒業 |
|---|---|
| 1997年 | 3月東京理科大学大学院理学研究科物理学専攻 修了 |
| 1999年 | 3月東京理科大学大学院理学研究科物理学専攻博士 修了 |
| 所属 | デザイン・データ科学部 デザイン・データ科学科 |
| 学位 | 1995年03月 学士(理学) 東京理科大学 |
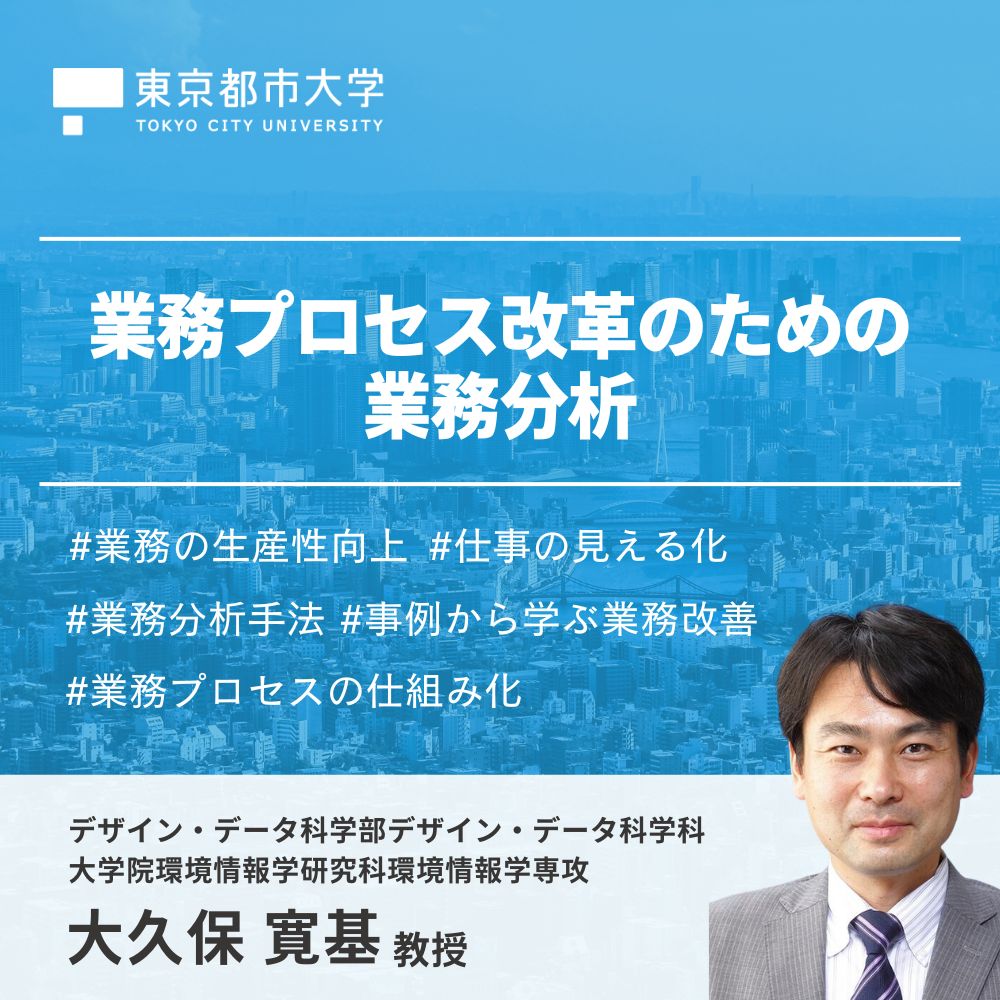
| 講義 | 業務プロセス改革のための業務分析 |
|---|---|
| 開講日 | 1コマ目 |
| 講師名 | 大久保 寛基 教授 |
| 前提知識 | 特になし |
| 事前準備 | 特になし |
企業において業務の生産性向上は、大変重要である。特に、サービス業における生産性は低いと言われており、生産性向上に役立つ取組みの例として、業務仕組み化の活動について学ぶ。業務仕組み化においては、現状の「見える化」が重要であり、そのためには、適正に業務を分析し、評価することで現状モデル(AS-ISモデル)として表現することが必要である。そして、生産性を向上できる改善された業務モデル(TO-BEモデル)の作成を目指すことの仕組みを学ぶ。効果的な改善を行うためには、改善対象業務を適切に捉える必要があり、そのためには、AS-ISモデル、TO-BEモデルを考えることができるためのモデリングの知識も学ぶ。

東京都市大学 |
|
| 所属 | デザイン・データ科学部 デザイン・データ科学科 |
|---|---|
| 1997年 | 早稲田大学理工学部工業経営学科 卒業 |
| 1999年 | 早稲田大学理工学研究科機械工学専攻経営システム工学専門分野修士 修了 |
| 2002年 | 早稲田大学理工学研究科機械工学専攻経営システム工学専門分野博士 単位取得満期退学 |

| 講義 | ビジネスで活用する統計学入門 |
|---|---|
| 開講日 | 1コマ目 |
| 講師名 | 斎藤 文 教授 |
| 前提知識 | Excel初級以上 |
| 事前準備 | PC(Excel) |
インターネットとスマートフォンの普及により、それらを通じて企業に蓄積されるデータは飛躍的に増加しています。これらのデータを上手に活用して、仕事の効率を上げ新しい価値を生み出すことが、どのような業務においても求められる時代になっています。そこでこの講義では、まず記述統計と推測統計の基礎について学びます。次に活用のひとつであるアンケート調査の方法とそのまとめ方について学びます。いずれもExcelを活用した演習を中心に実践的に活用できるデータ分析を体験することを目指します。数学の知識がないことを前提に、これまで統計学を学んだことがないという受講生を前提に講義を行います。

| 所属 | 東京都市大学デザイン・データ科学部デザイン・データ科学科 |
|---|---|
| 職名 | 特任教授 |
| 1984年 | 早稲田大学 理工学部 工業経営学科 卒業 |
| 1986年 | 早稲田大学 理工学研究科 機械工学専攻 工業経営学専修 |
| 1989年 | 早稲田大学 理工学研究科 機械工学専攻 工業経営学専修 |
| 1992年 | 早稲田大学 理工学部 助手 |
| 1997年 | 博士(工学) 早稲田大学 取得 |
| 1992年~2022年 | 産業能率大学情報マネジメント学部 教授 |
| 2023年~ | 現職 |
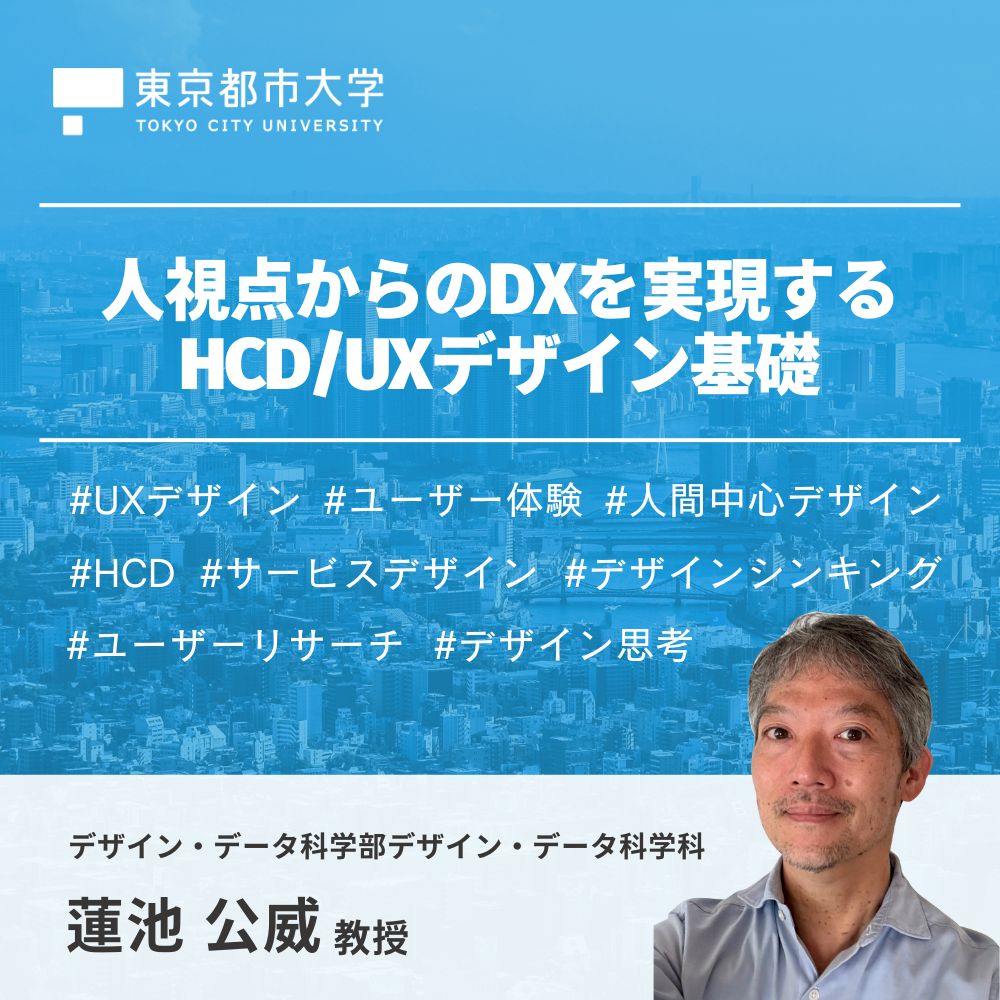
| 講義 | 人視点からのDXを実現するHCD/UXデザイン基礎 |
|---|---|
| 開講日 | 1コマ目 |
| 講師名 | 蓮池 公威 教授 |
| 前提知識 | ユーザー理解や顧客価値に関する興味があること |
| 事前準備 | PC |
DXスキル標準では、デザインのスキルを「顧客・ユーザー理解」「価値発見・定義」「設計」「検証(顧客・ユーザー視点)」「その他のデザイン技術」と定義しています。
本講義では、DXに関わるすべての人を対象に、これらのスキルの基盤である「人間中心デザイン(HCD)」と「UXデザイン」について、その目的と概要、背景、DXとの関係を解説し、人視点からの価値創出の基本的知識と基本プロセスを学びます。
また、事例研究とユーザー視点の演習を通じて、人視点のアプローチの「態度(Attitude)」を学び、今後実践していくための素地を作ることを目指します。

東京都市大学 |
|
| 1994年 | 京都工芸繊維大学 大学院 造形工学専攻修了。富士ゼロックスのデザイン部門で、UIデザイン、インタラクションデザイン、サービスデザインの実践とマネジメントに従事。 |
|---|---|
| 2022年 | 独立。デザイナー(デザインリサーチ/インタラクションデザイン)、株式会社フューチャーセッションズ 外部パートナーとして活動を開始。(現在も継続中) |
| 2023年 | 東京都市大学 デザイン・データ科学部 教授。 |
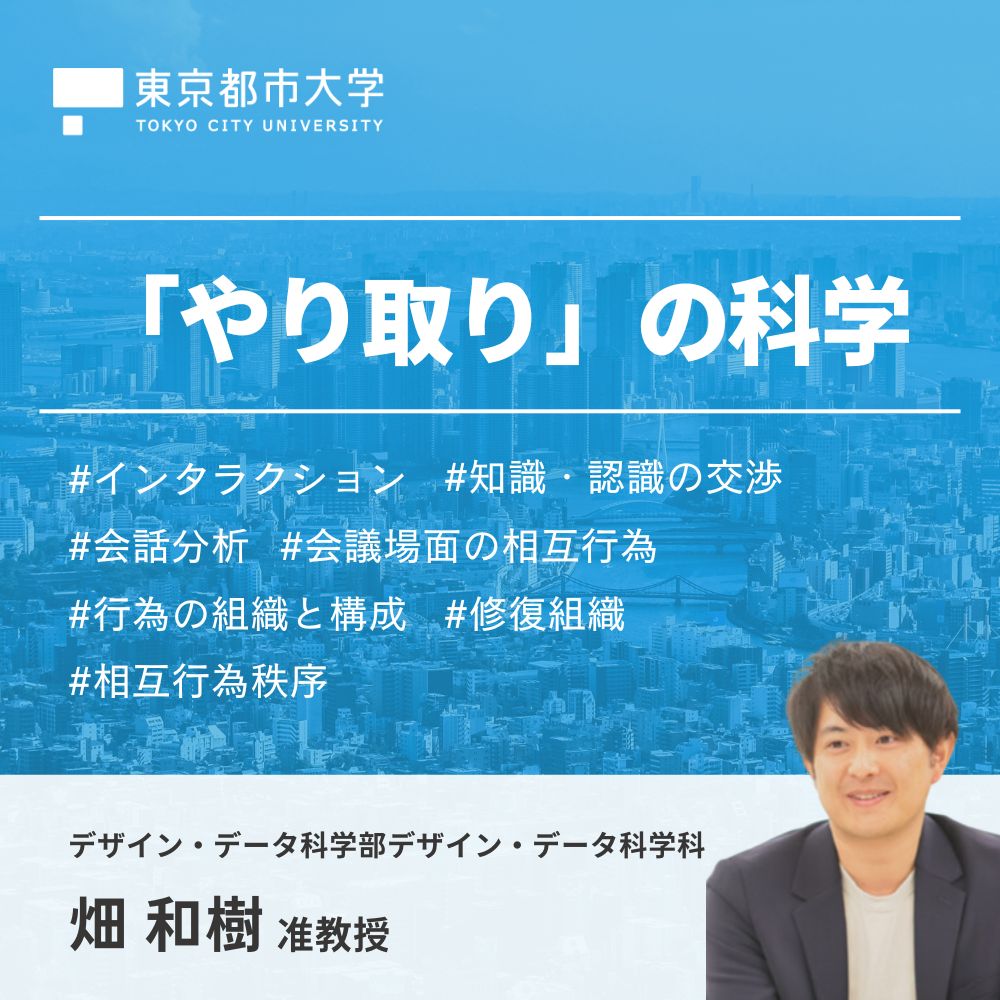
| 講義 | 「やり取り」の科学 |
|---|---|
| 開講日 | 1コマ目 |
| 講師名 | 畑 和樹 准教授 |
| 前提知識 | 特になし |
| 事前準備 | 特になし |
他者との「やり取り」(interaction = 相互行為)は、あらゆる社会活動の基盤であるとともに、人間が備える社会性を鮮明に映し出すものである。本科目では、ことば・身体行動の用いられ方を中心に、会話にみられる「手続き」を明らかにしていく。我々はいかなる活動を、何のために、どのような方法でやり遂げるのか。会話場面の分析演習を通じて、会話は決して無作為に成り立っているわけではない、いわば精巧な社会活動であることを見いだしていきたい。すでに様々な社会活動を経験している履修者にとって、相互行為のメカニズムを紐解いていくことは、安易に考えられがちな「コミュニケーション」の在り方を考える機会となることが期待される。

| 所属 | 東京都市大学 |
|---|---|
| 2010年 | 成城大学文芸学部英文学科 卒業 |
| 2012年 | 成城大学文学研究科英文学専攻修士修了 |
| 2013年 | Newcastle UniversitySchool of Education, Communication and Language SciencesMA in Applied Linguistics and TESOL修士(イギリス) 修了 |
| 2018年 | Newcastle UniversitySchool of Education, Communication and Language SciencesPhD博士(イギリス) 修了 |
| 学位 | 学士(文学) 成城大学 2010年 |

名前:
平野さん
業種・職種:
業種/不動産運営管理
職種/情報システム
会社内でDXのプロジェクトに関わることが多かったのですが、知識が豊富というわけではなかったため、検討・導入していくにあたり現状の知識、スキルでは人を巻き込んで成果を達成するのは難しいと感じていました。
そんな時に、東京都市大学DX人材育成コースの募集を知り、真っ先に応募いたしました。
経営層が積極的に関わり、企業のビジョンに対してどうDX化していくかを考えていくことが大事、というのは非常に衝撃を受けました。
こうした、DX化(IT化含む)は、各部署で効率化していくレベル感で色んなSaaSサービスを見つけて来ては失敗を繰り返しているといったことを耳にします。
しかし、上記の考えをどの講師の方も当たり前のように話されているのを見て、成功に導くにはこれが必須だと大きな学びになりました。
会社全体の動きを俯瞰して、本当に必要なDXは何か?誰を巻き込んで動かしていく必要があるか?
といったことを先に考えるようになりました。
普段、お会いできないような講師の方々の貴重な話が聞けるだけでも価値があります。
講義では講師ご自身が体験されてきたことや、達成するまでのプロセスを知ることができるので様々なヒントが散りばめられておりました。
意欲を持って参加することで、そのヒントから自身の知識やスキルに繋がるものが得られると思いますので、是非迷わず参加してみてください。

名前:
荒居さん
業種・職種:
業種/情報サービス業
職種/DX推進
東京都市大学の卒業生であり、IT分野でのキャリアを歩んできた者として、この度のDXプログラムには特別なご縁を感じて参加を決めました。卒業から20年以上が経過し、子育てによるキャリアブランク期間もありましたが、複数の企業で一貫してITに関わる仕事をしてきました。
現在のキャリアの基礎は、大学で情報系を学ぶことができたことが大きいと実感しており、最新の知識を母校でもう一度体系的に学びたいという思いがありました。
AIの歴史や仕組み、できること・できないことを講義にて体系的に学んだ結果、以前の漠然とした不安は好奇心へと変わり、これからのAI時代を前向きに受け止められるようになりました。
また、技術の絶え間ない進歩を肌で感じ、自己を常に更新(アップデート)し続けることの重要性を改めて深く認識する機会となりました。
「やり取りの科学」の講義では、DXを進める上で不可欠なコミュニケーションの本質に深く意識を向けることができました。
会話にみられる精巧な「手続き」や相互行為のメカニズムを紐解くことで、安易に考えられがちな「コミュニケーション」の在り方について、新たな視点を持つことができました。演習やディスカッションを通じて、現場で生かせる実践的な洞察を得られたのは大変有用でした。
データ分析の講義では、クラスタリングや回帰分析といった手法を学ぶだけでなく、分析結果を導き出す分析する側の思考力、そしてその結果を他者に理解してもらい、行動を促すための伝える力が不可欠であることを痛感しました。
この学びは、私の仕事に対する姿勢を大きく変えるきっかけとなりました。
このように深い学びが得られる本プログラムは、卒業生であるか否かにかかわらず、DXや最新技術に関心を持つ全ての方に自信を持っておすすめできます。
少しでも興味を持たれた方は、ぜひ参加してこの学びの場を体験してほしいと思います。