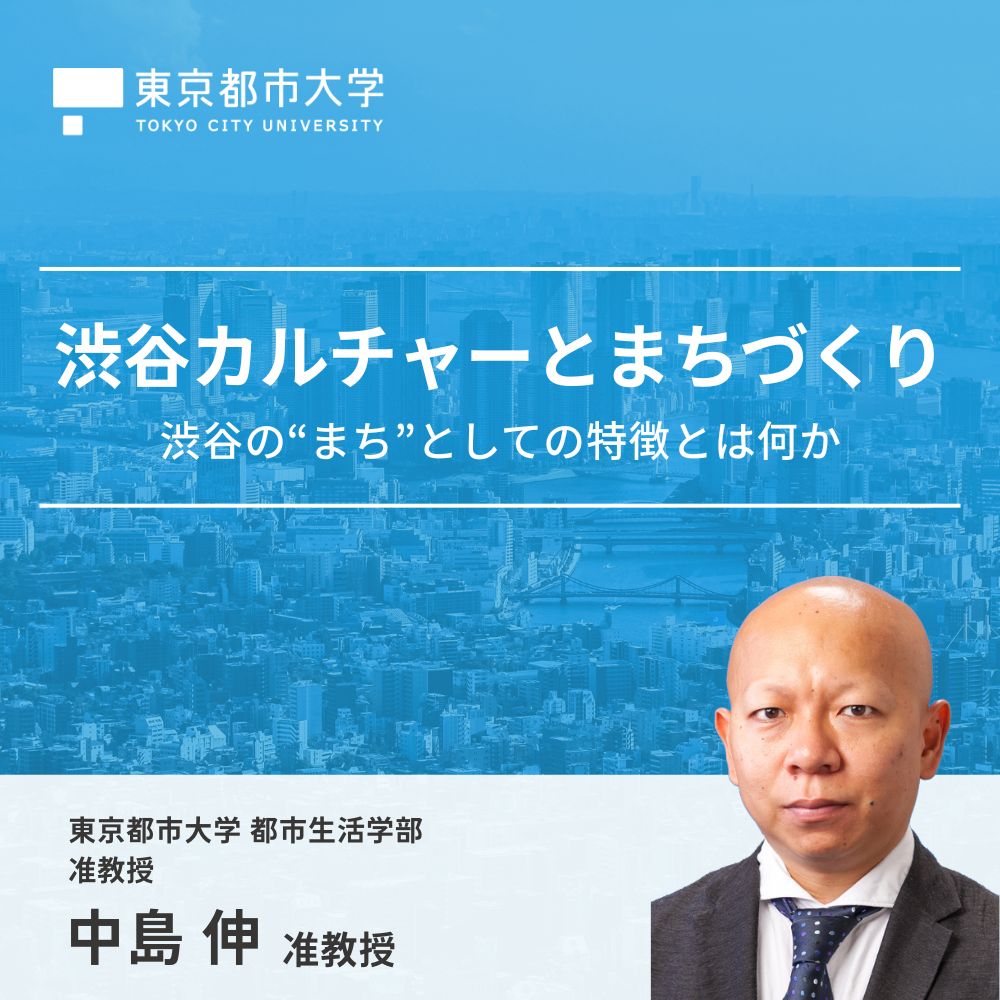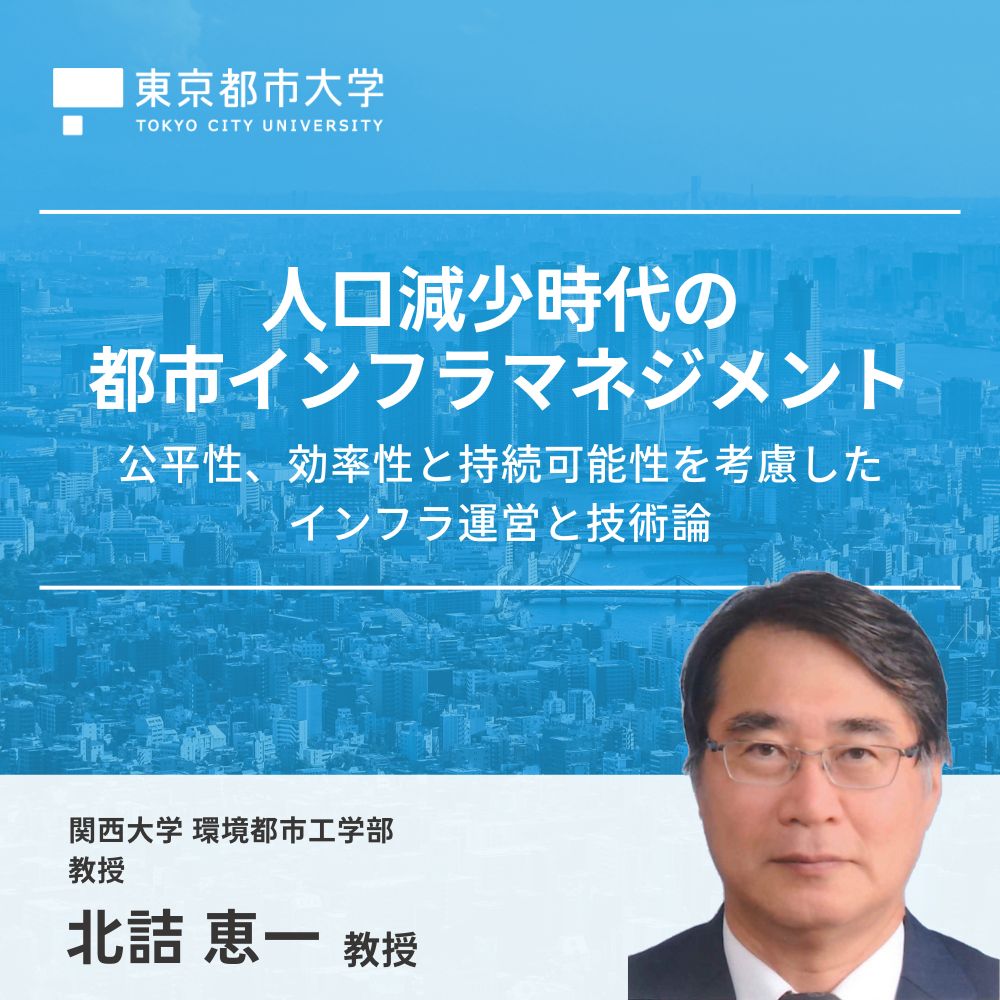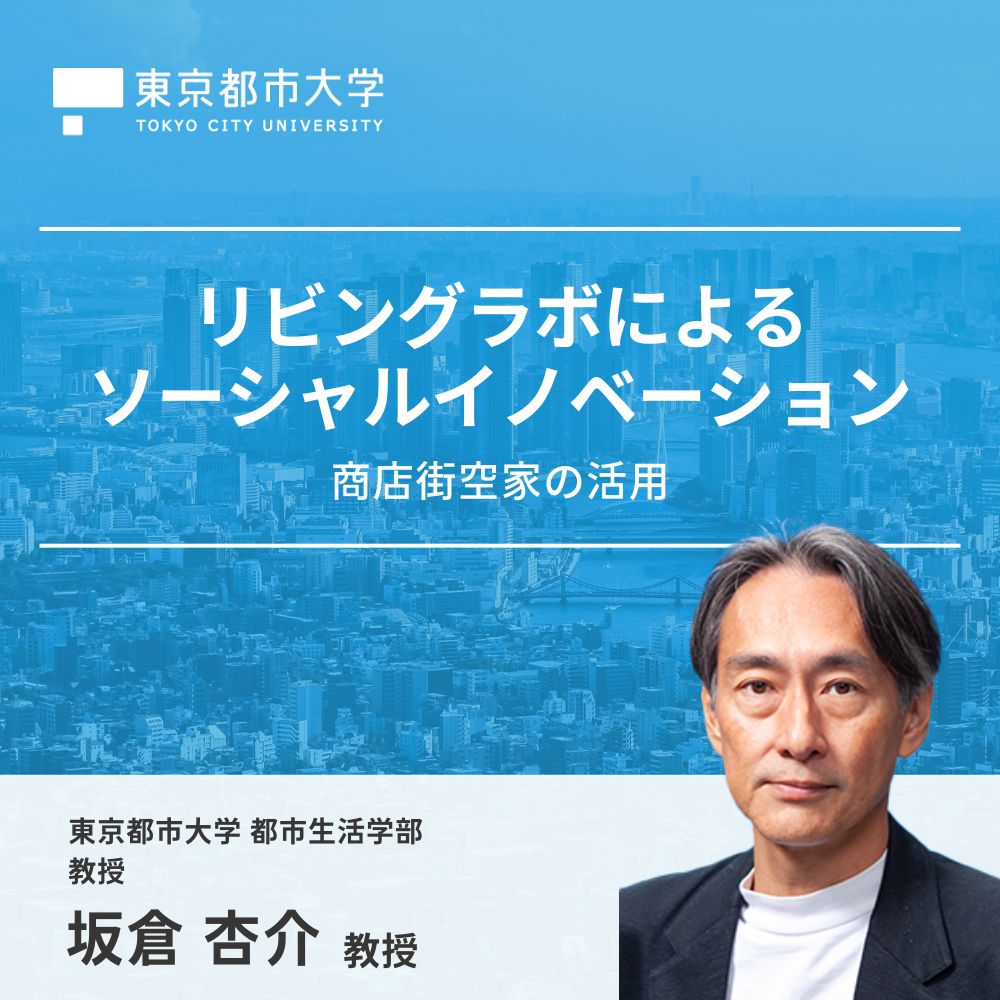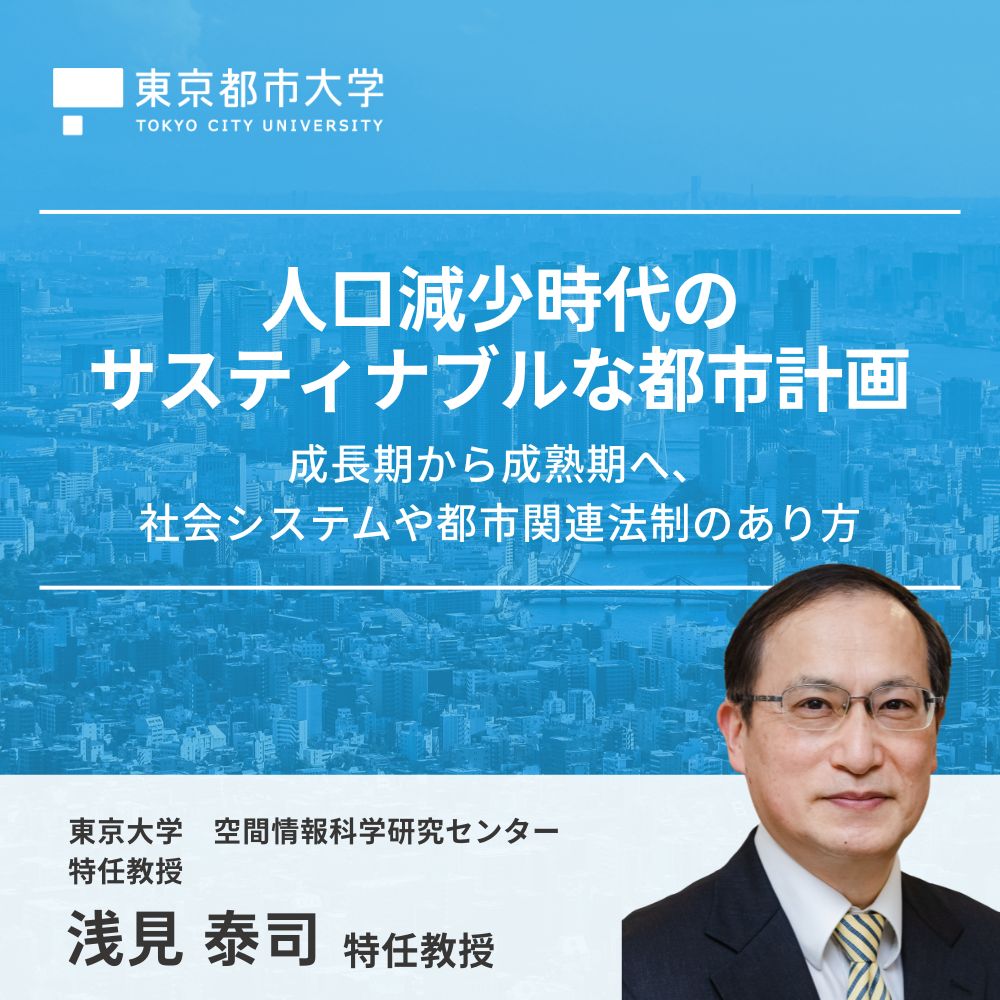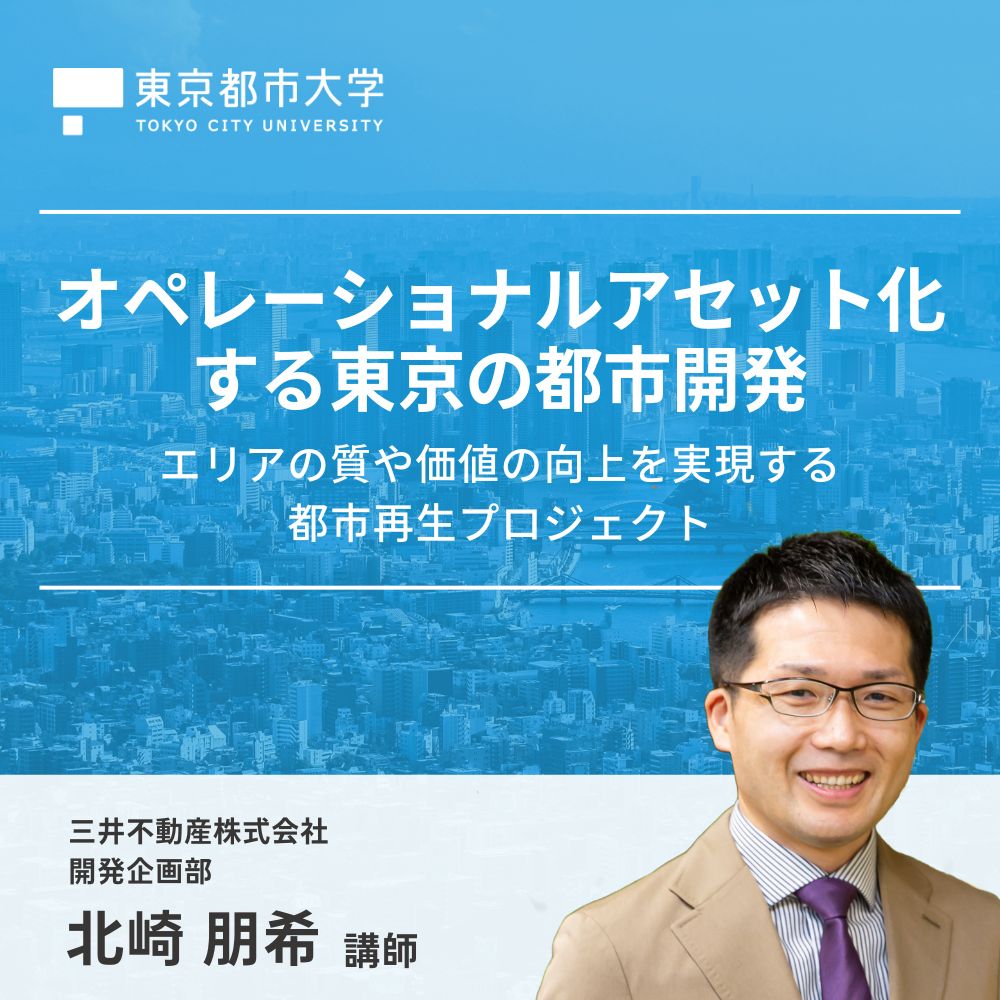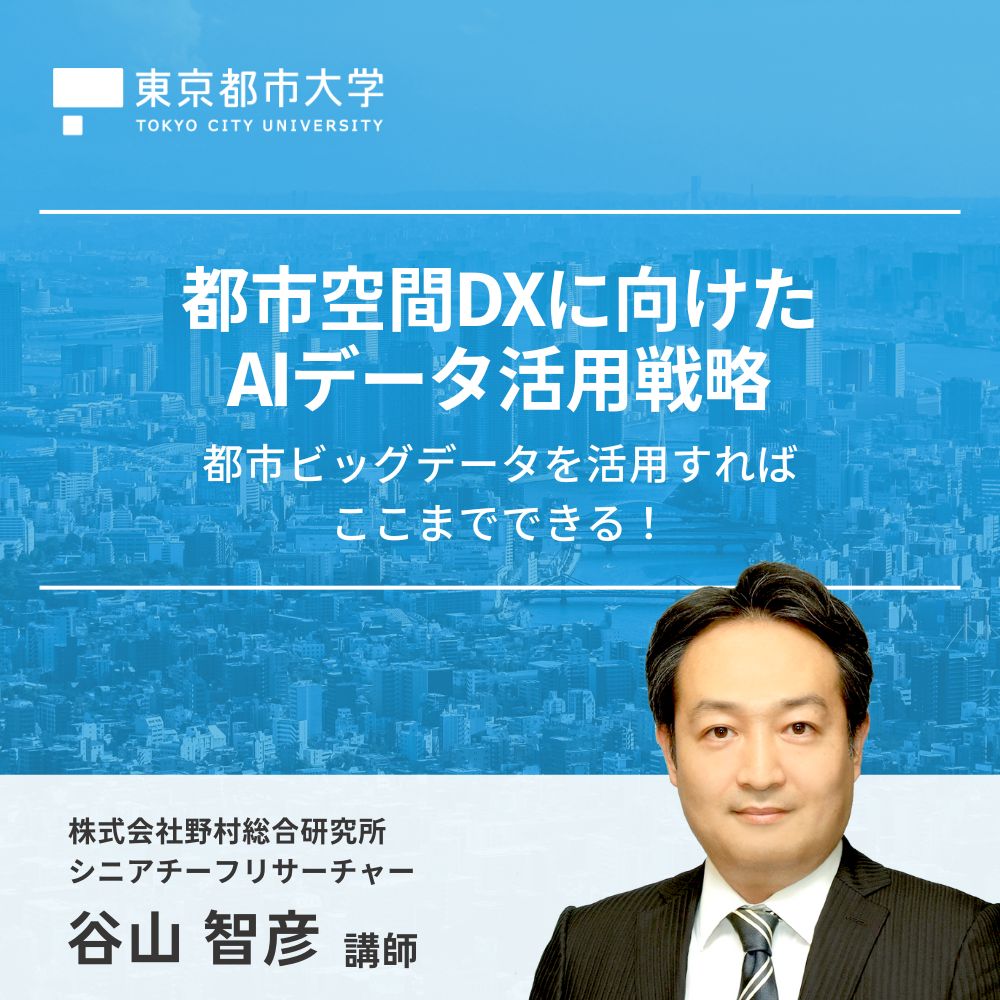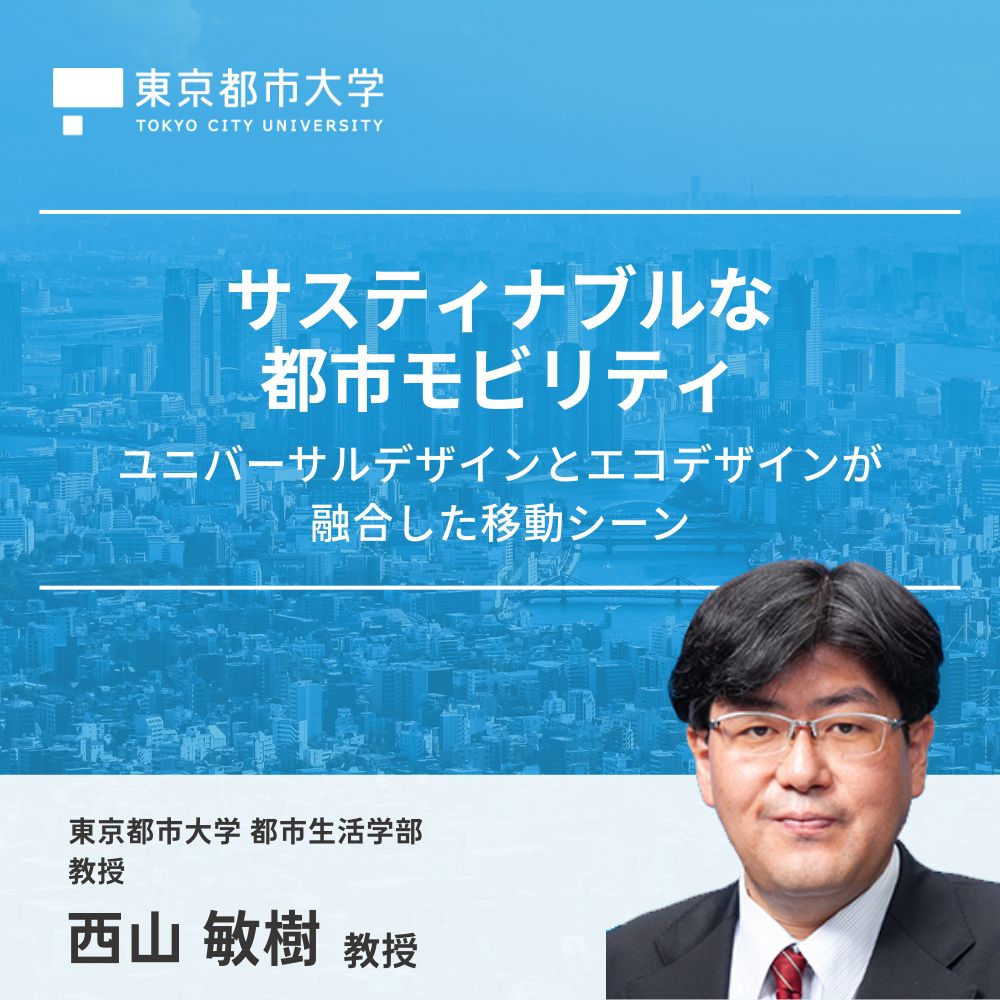コース編成
授業スケジュール


授業詳細
-

Sustainable Urban Management 概論
-
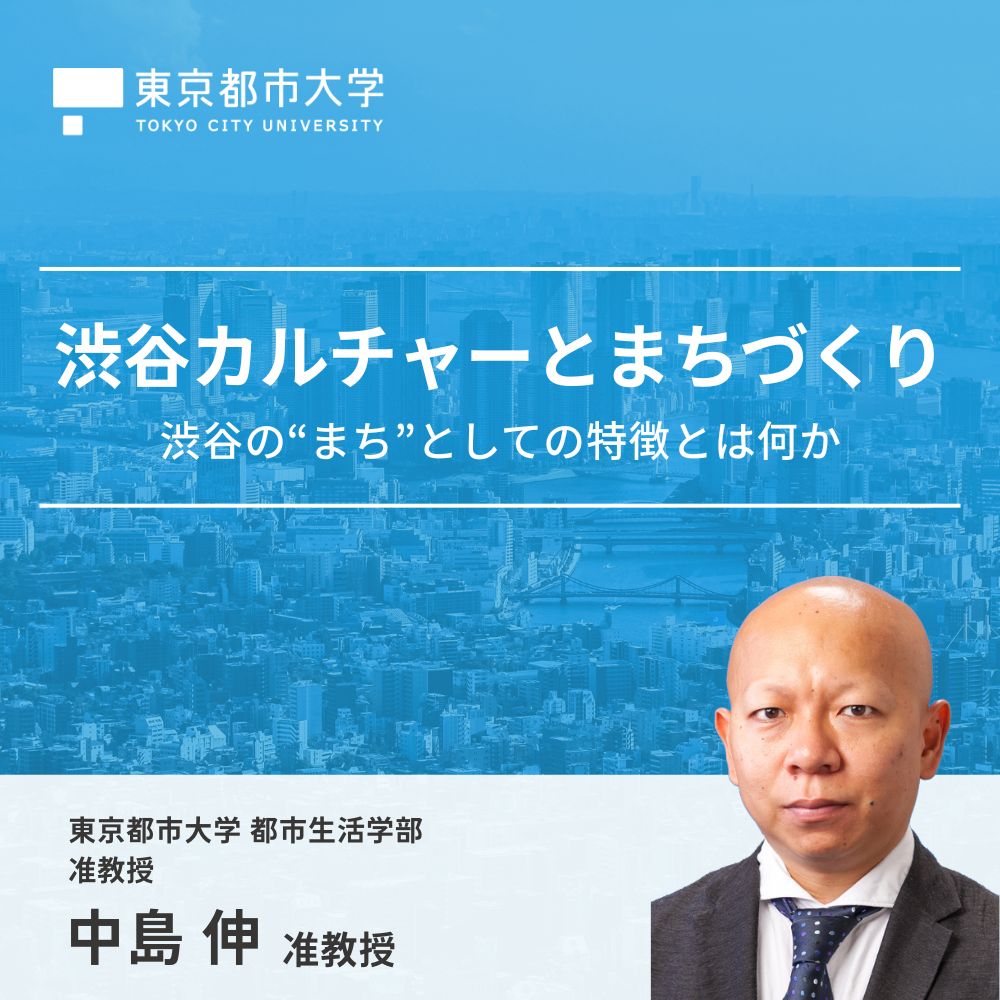
渋谷カルチャーとまちづくり
-

渋谷再開発とサスティナビリティ
-
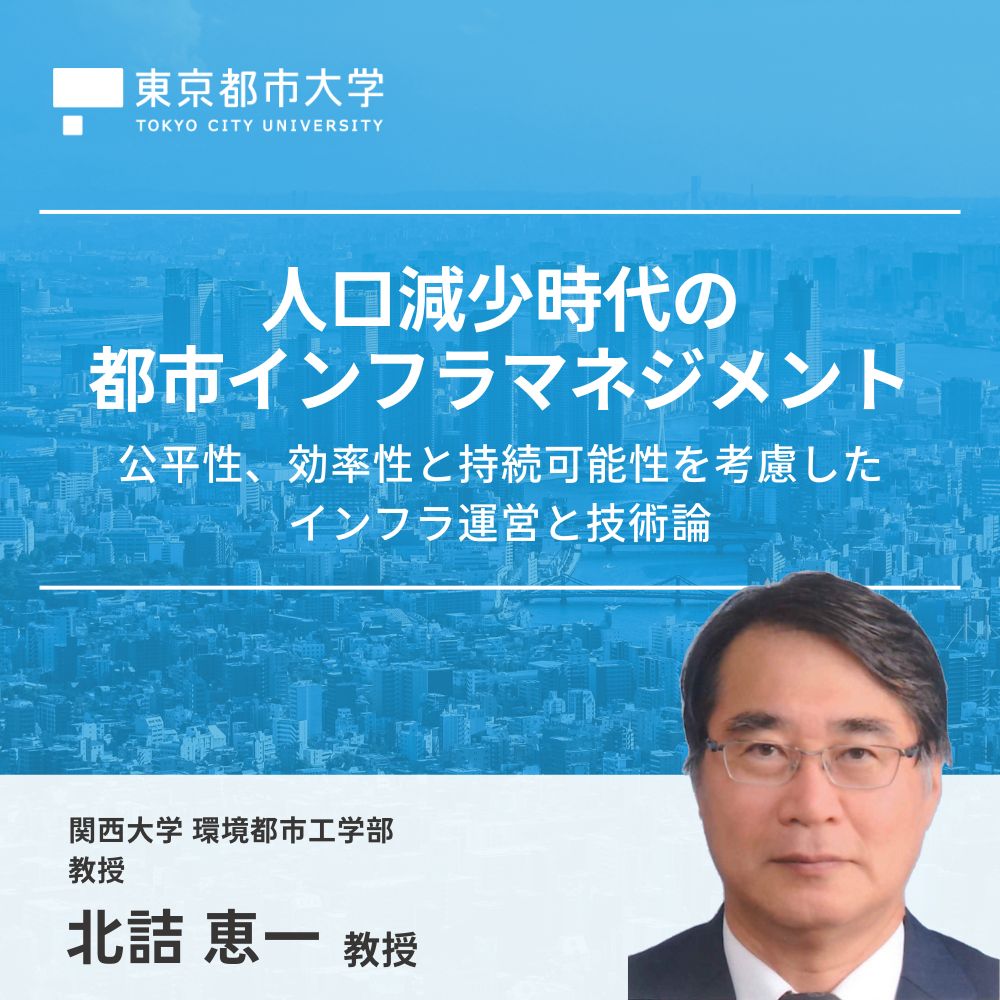
人口減少時代の都市インフラマネジメント
-

都市インフラの民間ファイナンス
-
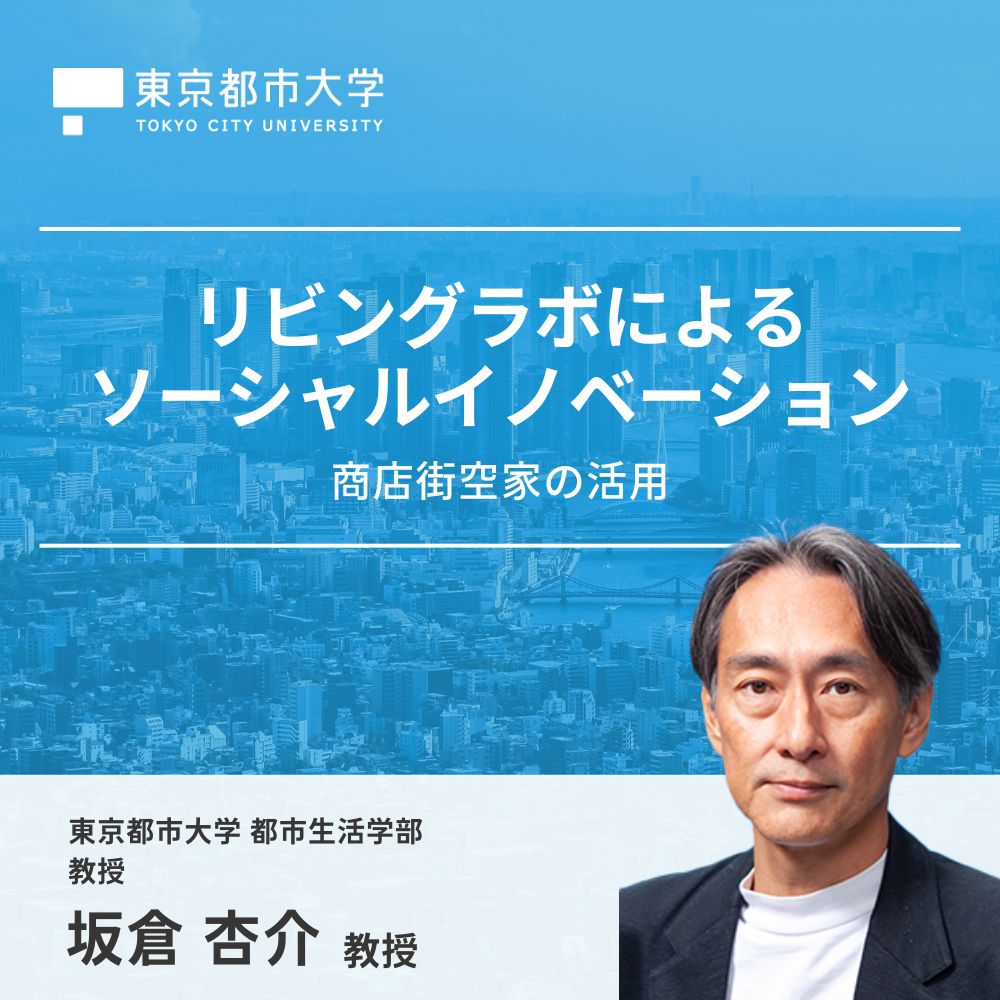
リビングラボによるソーシャルイノベーション
-

PPP、PFIに関する法制
-
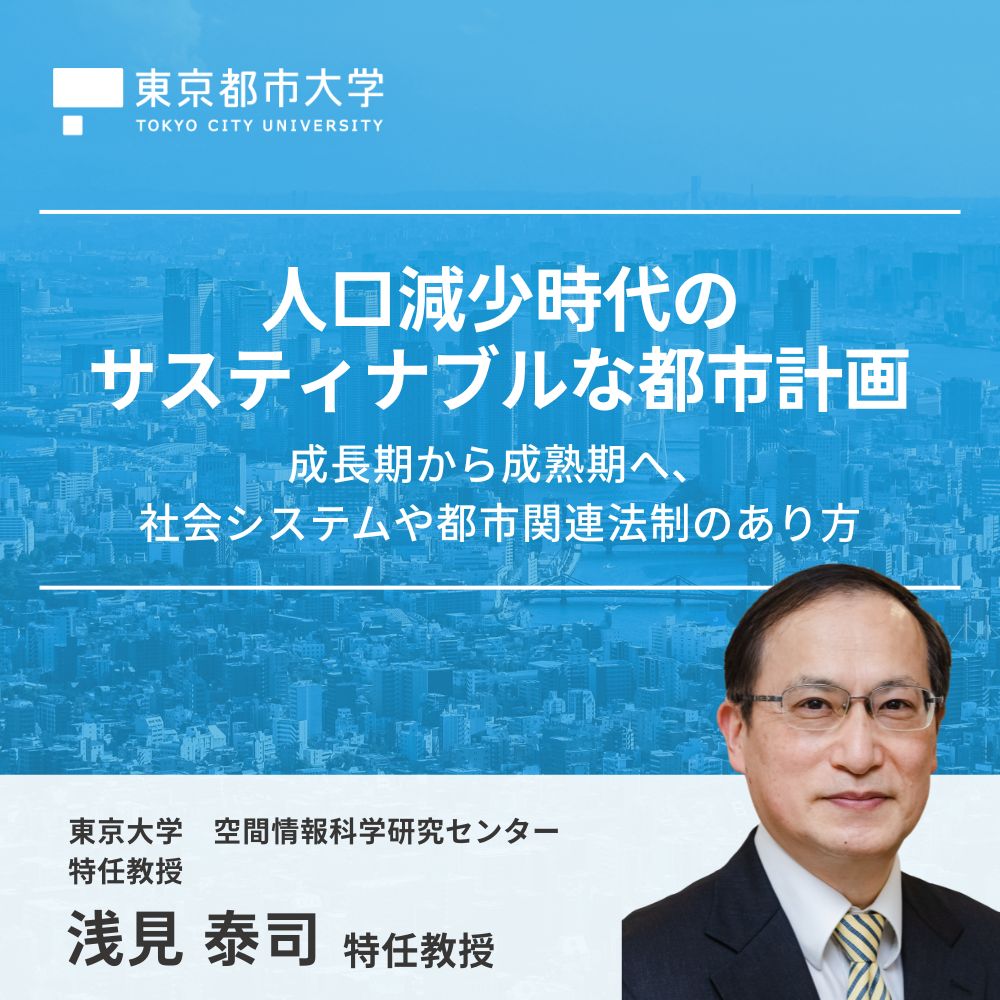
人口減少時代のサスティナブルな都市計画
-
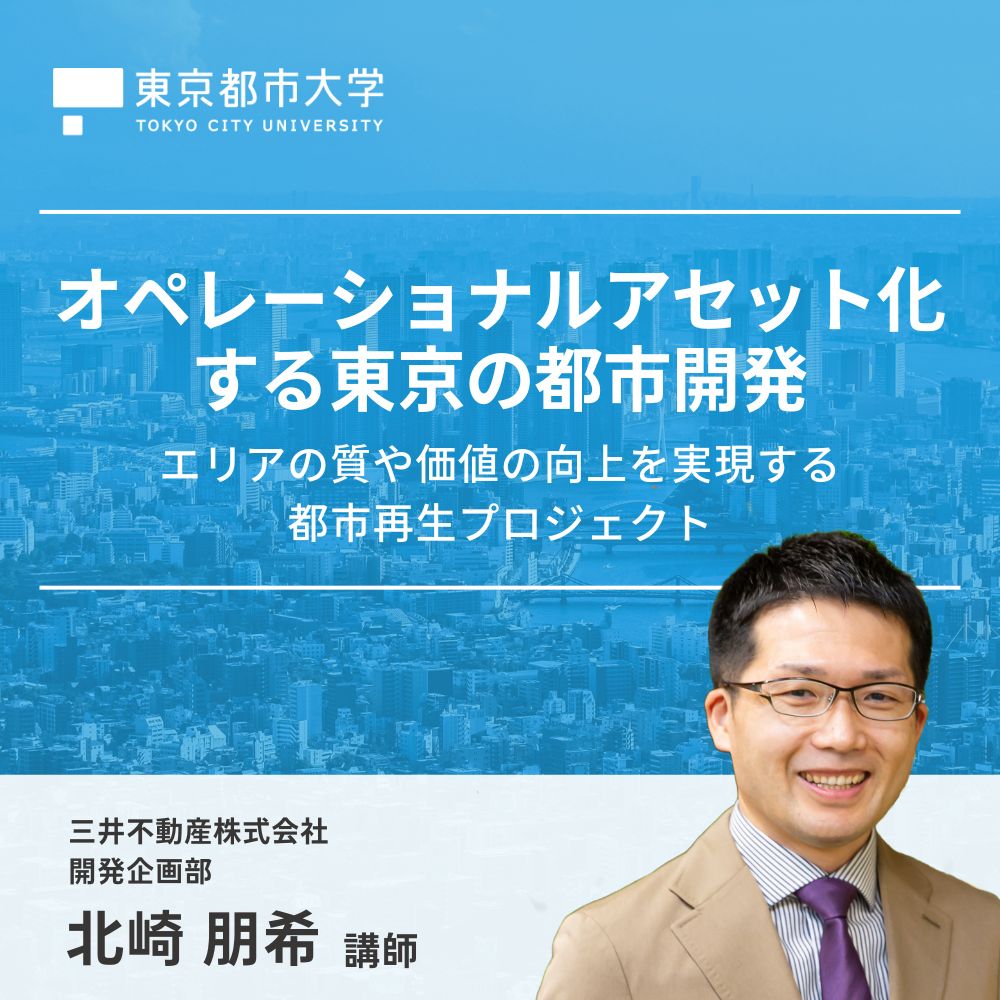
オペレーショナルアセット化する東京の都市開発
-
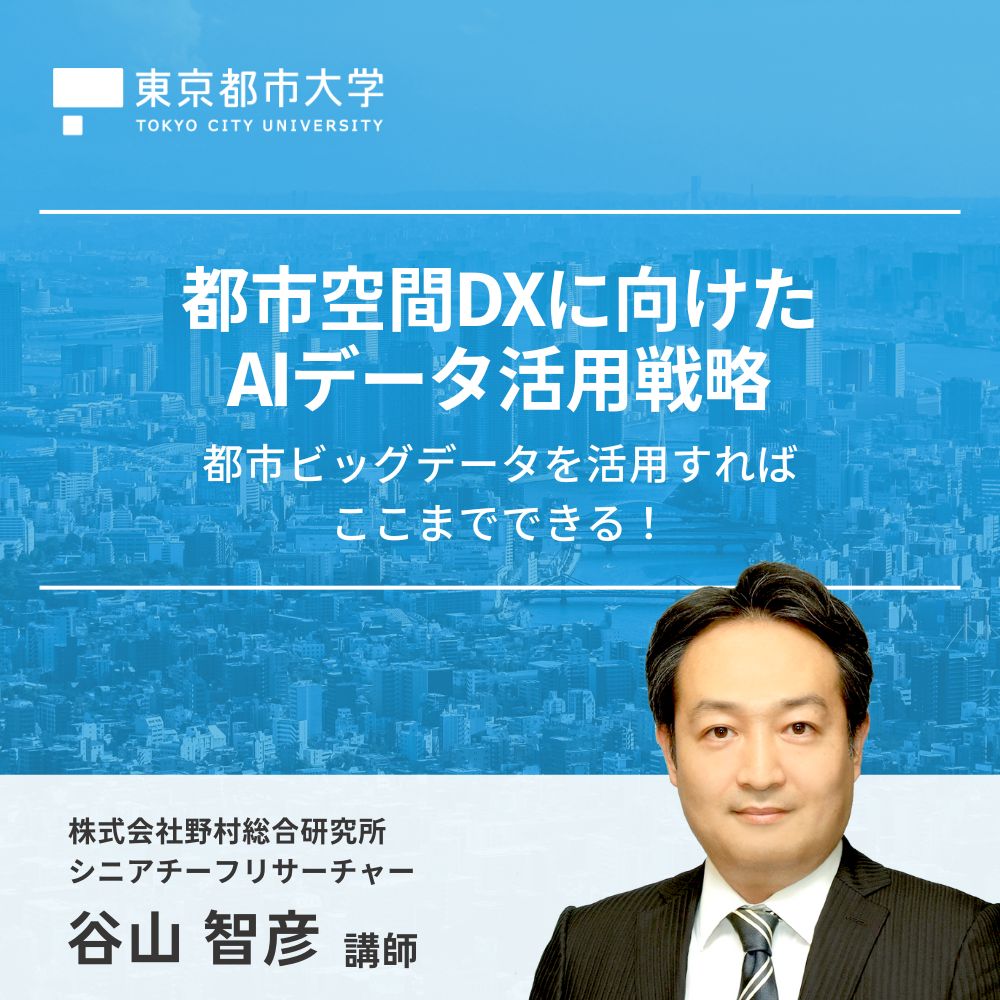
都市空間DXに向けたAIデータ活用戦略
-

都市・不動産とサスティナブルファイナンス
-
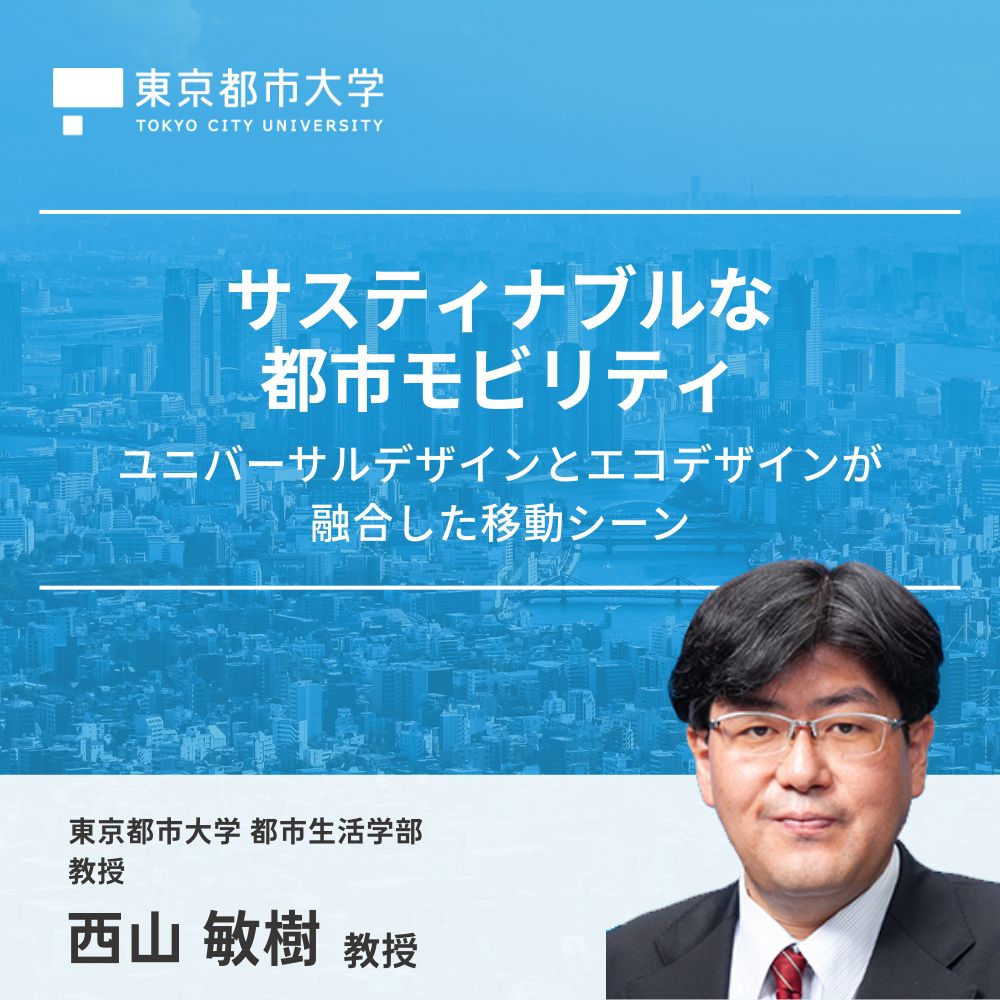
サスティナブルな都市モビリティ
-

脱炭素社会構築に向けた経営戦略
-

サスティナブルな都市とエリアマネジメント
-
Sustainable Urban Management 概論
宇都正哲
-

講義 Sustainable Urban Management 概論 – 人口減少の本質的意味とこれからの都市インフラ整備のトレンドとは何か
講師名 宇都正哲 講義概要
都市のSustainabilityを実現するには、人口減少、少子高齢化社会における都市縮退の時代をいかに生き抜くかに掛かっている。
これまでの成長期における社会システムやビジネスモデルは、人口減少のトレンドの中では通用しない。
では、どのように住民が減少するなかで持続可能でウェルビーイングを維持する政策を考えていくべきか?
また、企業にとっては将来的に国内マーケットが縮小することに伴いトップライン(売上)が減少するなか、いかに持続的な成長を実現するか?
これらの諸課題は日本の多くの政府・自治体、企業にとって共通の課題である。
この講義では、それらに向き合うため、人口減少や少子高齢化がもたらす影響を正確に理解するとともに、いくつかの重要な視点を議論するとともに、参考となる具体的なケーススタディをもとにその処方箋を探る。講師紹介

所属 東京都市大学 都市生活学部
役職 東京都市大学 大学院環境情報学研究科都市生活学専攻 教授 兼 都市生活学部 学部長 教授
経歴 1969年生まれ。
東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻博士課程修了 博士(工学)。
1991年に株式会社野村総合研究所に入社。
都市・地域関連の受託研究、都市インフラビジネスの事業戦略、海外展開におけるパートナリング、不動産ビジネスの事業戦略などを専門に25年間にわたり戦略コンサルティングを実施。都市インフラセクターのヘッドとして、同社のコンサルティングチームを長年にわたり牽引し、社長賞を3回受賞。経営戦略、新規事業推進、M&A、海外展開等のコンサルティングや政策提言を行い、これまでに300プロジェクト以上のコンサルティング経験を有する。
現在は、東京都市大学 大学院環境情報学研究科都市生活学専攻 教授 兼 都市生活学部 学部長 教授として、不動産マネジメント研究室を主宰。 -
渋谷カルチャーとまちづくり
中島 伸
-
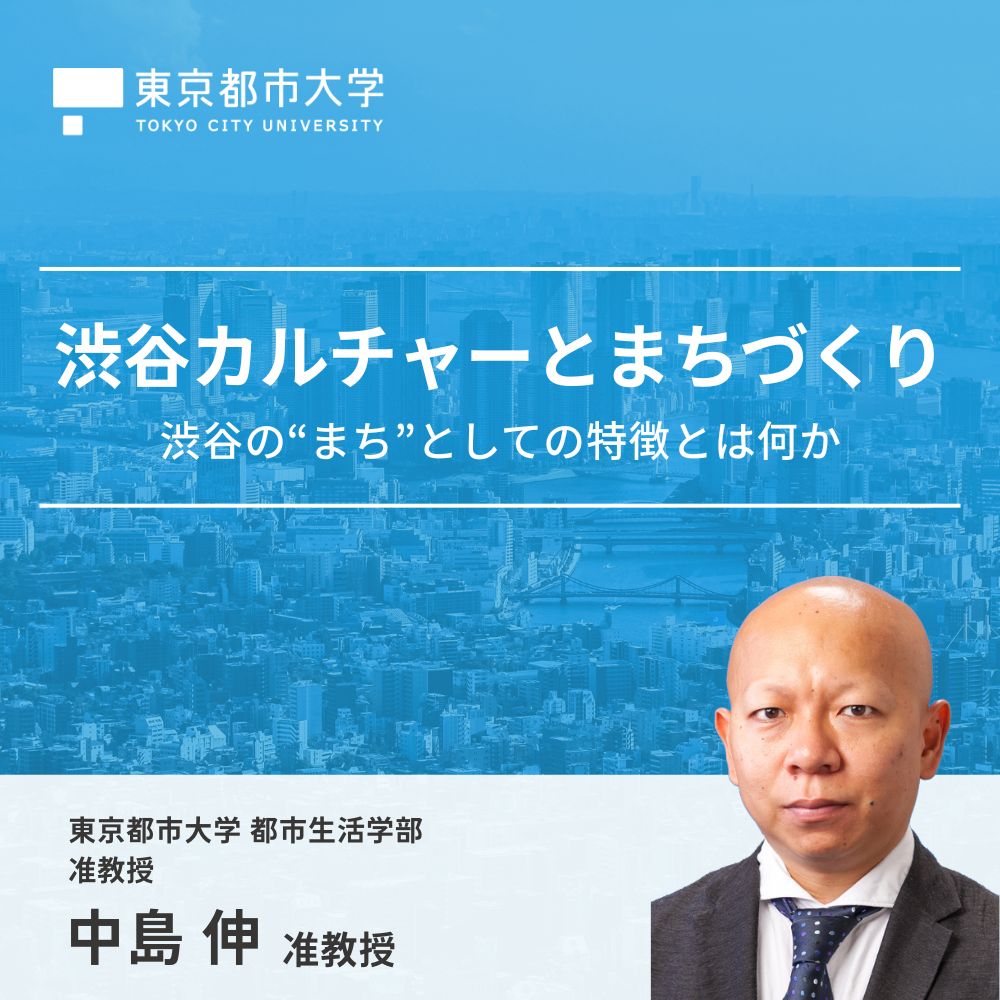
講義 渋谷カルチャーとまちづくり - 渋谷の“まち”としての特徴とは何か
講師名 中島 伸 講義概要
都市再生特別措置法が施行されて20年が経ちます。都市再生としての再開発事業は2030年代に向けて完成しつつある渋谷において、これからのまちづくりにおいて重要となる要点としての個性ある文化的な都市デザインとその進め方について、渋谷のまちづくりの現場での議論を踏まえて、講義にて展望します。コロナ禍を経て、価値転換した都心部において、インバウンドの影響の先の都市のビジョン構築と実践について考えます。
講師紹介

所属 東京都市大学都市生活学部
役職 准教授
経歴 1980年東京都生まれ。都市デザイナー、博士(工学)。
2013年東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻修了、(公財)練馬区環境まちづくり公社練馬まちづくりセンター専門研究員、東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻・助教を経て、2017年より現職。
専門:都市デザイン、都市計画史、公民学連携のまちづくり。
アーバンデザインセンター坂井副センター長、渋谷再開発協会渋谷計画2040エリアビジョン委員会委員長、千代田区神田警察通り沿道整備推進協議会神田警察通り周辺まちづくり検討部会長、東京文化資源会議トーキョートラムタウン構想座長を歴任。
受賞歴:日本都市計画学会論文奨励賞、日本不動産学会湯浅賞(研究奨励賞)博士論文部門受賞/著書:『図説都市空間の構想力』(学芸出版社・2015)、『時間の中のまちづくり 歴史的な環境の意味を問い直す』(鹿島出版会・2015)、『商売は地域とともに 神田百年企業の足跡』(東京堂出版・2017)、ほか。 -
渋谷再開発とサスティナビリティ
坂井 洋一郎
-

講義 渋谷再開発とサスティナビリティ– 渋谷におけるサスティナブルな開発要素とは何か
講師名 坂井 洋一郎 講義概要
東京のインバウンド訪問先として二年連続トップ(67.1%)の渋谷。人々を惹きつける磁力とは。
100年に一度の大改造中の渋谷はここに至る間、関東大震災の震災復興、大戦後の戦災復興、1964年の東京オリンピックと三度の機会を契機とした都市改造が行われてきた。
東急は1918年渋沢栄一により設立された田園都市(株)を源流とし鉄道事業と共に沿線の街づくりを先導してきた。渋谷はそのヒンターランドを支える副都心として、1927年に東横線が渋谷に乗り入れ、東急は約100年渋谷の街のプラットフォーム創りをハード、ソフト両面で担ってきた。
渋谷には多様性、包摂性が培われ、新しい文化やクリエイティブ産業が勃興してきており、今も尚人々が集い、刺激し合いその勢いは力強い。それは何故なのかを考察していく。講師紹介

所属 東急株式会社
役職 執行役員 都市開発本部 渋谷開発事業部長
経歴 早稲田大学大学院理工学研究科 建設工学専攻 都市計画研究室
1990年 東京急行電鉄株式会社(現東急)に入社。
35年一貫して都市開発のプランナーとして、コンセプト創りからの計画立案、フィージビリティスタディ、設計・施工対応、行政・地元対応、運営管理のセットアップ等々一連の開発業務を担い商業施設、オフィス、住宅、ホテル等々を国内外で創り上げてきた。
【実績】
当社沿線:日吉、武蔵小杉、田園調布、目黒駅等の駅ビルの開発を担当。
都心部:コレド日本橋、キャピトル東急タワー、東急番町ビル、渋谷キャスト等を担当。
2011年より国際部門にて主にベトナムを中心に取り組み、7年ほどのホーチミンへの赴任を通じ、高度経済成長下のベトナムにおいて大規模都市開発を担当。
2021年より現職 渋谷における次の100年に向け、社会の変容を睨みつつ世界の渋谷としての都市空間形成に取り組む。 -
人口減少時代の都市インフラマネジメント
北詰恵一
-
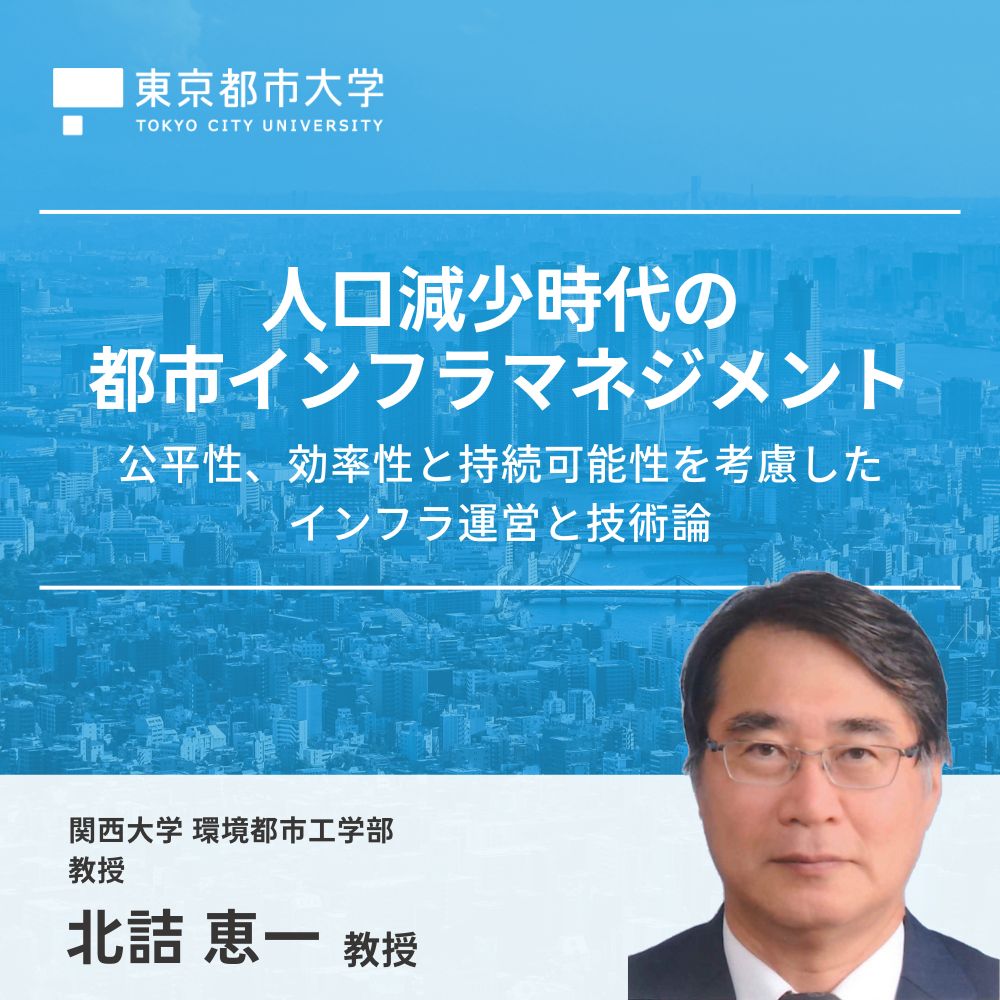
講義 人口減少時代の都市インフラマネジメント – 公平性、効率性と持続可能性を考慮したインフラ運営と技術論
講師名 北詰恵一 講義概要
人口減少時代の都市インフラの整備・運営は,効率性,公平性に加え,持続可能性の視点からのマネジメントが求められる。
そのための技術論は必ずしも十分ではなく,新たな考え方の導入やいくつか見られる先進技術の位置づけ直しなどを通じて,将来世代のインフラサービスへのニーズを満たすマネジメント技術とすべきである。
総費用や1人当たり費用の削減、環境負荷軽減・省エネルギー化、ネットワーク効率や維持管理水準の低下に対応したモニタリング、人材確保と技術継承の中長期計画など、多方面にわたる体系的な議論が必要となる。
本講義では、これらの3側面から見て、人口減少下に求められるインフラ技術のあり方について考える場としたい。講師紹介

所属 関西大学 環境都市工学部
役職 関西大学環境都市工学部 副学部長,教授
先端科学技術推進機構 地域再生センター長経歴 1989年 (株)野村総合研究所に入社。研究員として、国・自治体の地域政策・交通施設計画調査業務に携わる。
1996年 東北大学助手。土地利用・交通モデル、費用便益分析、世代間公平性を専門とする。
2001年 博士(工学)取得。
2002年 関西大学工学部専任講師。2004年に助教授、2007年に准教授。
2002~2013年 国立滋賀大学産業共同研究センター客員研究員兼務。自治体職員への学び直しを担当。
2015年 同大学環境都市工学部教授。土地利用・交通モデルをマイクロシミュレーション型に展開。人口減少下での社会資本計画や官民連携(PPP/PFI)に関心を広げる。
2021年 同大学先端科学技術推進機構地域再生センター長就任。古民家・空き店舗を改装して地域再生の拠点とする活動を実施。 -
都市インフラの民間ファイナンス
木村耕平
-

講義 都市インフラの民間ファイナンス – インフラ整備の裏側で暗躍?している民間ファンド
講師名 木村耕平 講義概要
人口と経済が右肩上がりの時代には長期のファイナンス(税金等公共財源を含む)でインフラを整備し、将来の発展・成長に寄与するというモデルが中心であったが、人口が急速に減少へ向かっていく時代においてインフラ整備を支えるファイナンスも適切な変化を求められる。
DXやAIの活用を含め、インフラ整備における民間ファイナンスの特徴や役割、特にインフラファンドの状況や特徴などについて学ぶ。
インフラ整備を計画し実施していく主体(公共やユーティリティ企業等)、インフラ整備や運営の担い手となる民間企業、あるいはインフラ整備へ資金を提供する金融機関等、いずれにおいても、これからのインフラファイナンスのトレンドと本質を理解することは重要である。講師紹介

所属 SUEZ (Singapore) Services Pte. Ltd.
役職 ディレクター、PPP/BOTデベロップメント
経歴 2001年 丸紅株式会社。国内外のPPP/PFIやM&Aに従事。特に上下水道案件多数
2008年 マッコーリー証券株式会社。多様なインフラ案件のアドバイザリー
2011年 伊藤忠株式会社。海外の上下水道・廃棄物案件PPP/PFIやM&Aに従事
2016年 経営競争基盤
2018年 E&Yトランザクションアドバイザリーサービス
2022年 SUEZ。国内外の上下水道・廃棄物PPP/PFI案件・M&Aに従事。2022年後半より東南アジア市場の開発責任者 -
リビングラボによるソーシャルイノベーション
坂倉杏介
-
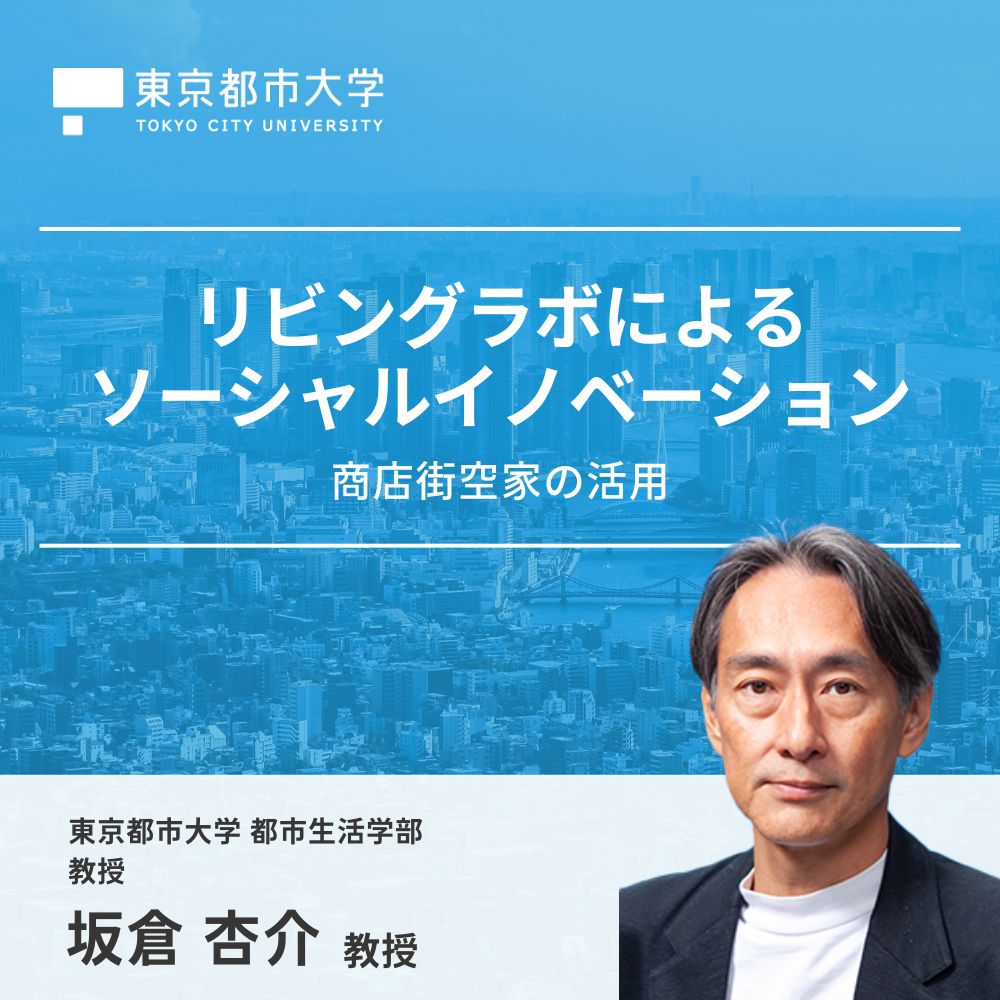
講義 リビングラボによるソーシャルイノベーション – 商店街空家の活用
講師名 坂倉杏介 講義概要
リビングラボは、オープンイノベーション2.0フレームワークを前提に、市民、企業、研究機関、行政の4セクターの共創によって新たな社会システムを生み出す仕組みです。
日本でも近年、地域や企業のイノベーションの鍵として注目され、事例も増えていますが、そうした知見を、みなさんの現場でどのように取り入れ、活用することができるでしょうか。
本講義では、リビングラボを通じたイノベーションのマネジメントについてわかりやすく解説するとともに、本学の地元尾山台に設置された「おやまちリビングラボ」を事例に、日本らしいウェルビーイングな「15分都市」に向けてどのような取り組みが可能か、その展望を議論します。講師紹介

所属 東京都市大学 都市生活学部
役職 教授
経歴 1972年生まれ。
慶應義塾大学大学院博士後期課程単位取得退学。博士(政策・メディア)。
専門はコミュニティマネジメント。一般社団法人三田の家代表理事、NPO 法人エイブルアートジャパン理事ほか。
多様な主体の相互作用から新しい価値を生み出す「共創プラットフォーム」という視点から、ウェルビーイングとイノベーションを実現するコミュニティ形成を実践的に研究している。現在は、大学の地元・尾山台ハッピーロード商店街に「おやまちリビングラボ」を設置、ウェルビーイングな日本型「15分都市」に向け、市民、行政、民間企業との分野を横断した共創プロジェクトを多数進行中。
共著に『わたしたちのウェルビーイングをつくりあうために その思想、実践、技術』(BNN出版)
『コミュニティマネジメント つながりを生み出す場、プロセス、組織』(中央経済社)
『場づくりから始める地域づくり 創発を生むプラットフォームのつくり方』(学芸出版社) -
PPP、PFIに関する法制
高橋玲路
-

講義 PPP、PFIに関する法制 – 主体論とリスク分担論からみた日本のPPP法制の特殊性
講師名 高橋玲路 講義概要
都市インフラは、それ自体公益的機能を持つため、その整備や運営には必ず公的主体の関与があります。
特に近年は自治体の財源問題やDX等の新技術導入、民間的経営視点による事業改善の必要性から、官民が一体となって都市インフラ整備や社会課題の解決に取り組むPPP/PFIの手法が広く用いられています。
他方で、我が国の法制は官と民とを峻別する傾向が強いため、PPP/PFIを実行する際に法制度と整合的な仕組みづくりが重要となります。本講義では、PPP/PFIに関係する法制度の背景や現在の姿を理解し、プロジェクトの具体的なデザインのポイントを学びます。講師紹介

所属 アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業
役職 パートナー弁護士
経歴 1995年 東京大学法学部卒業
1997年 弁護士登録
2001年~2002年 英国Allen&Overyでプロジェクトファイナンス案件に従事
2005年 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー就任
2020年 内閣府民間資金等活用事業推進委員会(PFI推進委員会)専門委員
弁護士として28年の実務経験があり、専門分野はPFIや再生可能エネルギーを含む、広くインフラを対象にしたプロジェクトファイナンス案件、空港、上下水道等のインフラストラクチャーを中心に社会基盤・地域開発に関連する各種PFI/PPP案件に多数従事し、政府機関、自治体、企業、金融機関を代理。 -
人口減少時代のサスティナブルな都市計画
浅見泰司
-
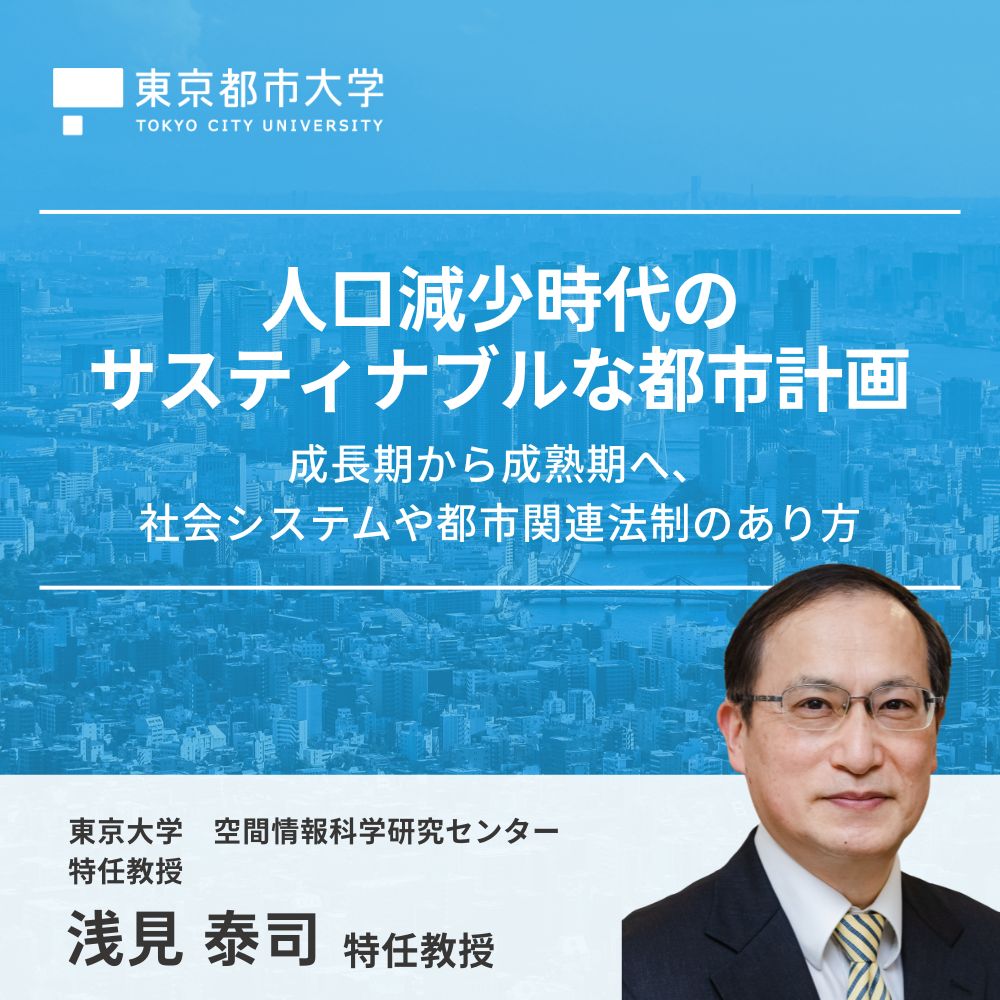
講義 人口減少時代のサスティナブルな都市計画 – 成長期から成熟期へ、社会システムや都市関連法制のあり方
講師名 浅見泰司 講義概要
現行の都市計画法は高度成長期のさなか1968年に制定された。
当時は、大都市への人口集中と都市構造をいかに調和させるかが問題であり、人口増加社会における市街地のコンパクト化を進めるための精度として整備された。
このため、主として開発の上限をコントロールする仕組みとなっており、この法制度の基本的な構造は現在も引き継がれている。
ところが、現在は多くの都市で人口減少に直面しており、市街地のスポンジ化が進む中で市街地の縮小をいかにコントロールするかが問われている。
そのためには、現在の都市計画の仕組みを抜本的に改革してく必要がある。本講義では、現行制度の問題点とその対処の方向性を論じる。講師紹介

所属 東京大学 空間情報科学研究センター
役職 特任教授
経歴 1987年 ペンシルヴァニア大学地域科学専攻博士課程修了(Ph.D.)
1987-1990年 東京大学工学部助手
1990-1992年 東京大学工学部講師
1992-2001年 東京大学工学部助教授
2001-2012年 東京大学空間情報科学研究センター教授
2010-2014年 東京大学空間情報科学研究センター長
2012-2025年 東京大学大学院工学系研究科教授
2017-2020年 東京大学大学工学系研究科副研究科長
2020-2023年 東京大学副学長
2021年- 東京大学大学総合教育研究センター長
2023年- 東京大学執行役・副学長
2025年- 東京大学空間情報科学研究センター特任教授 -
オペレーショナルアセット化する東京の都市開発
北崎朋希
-
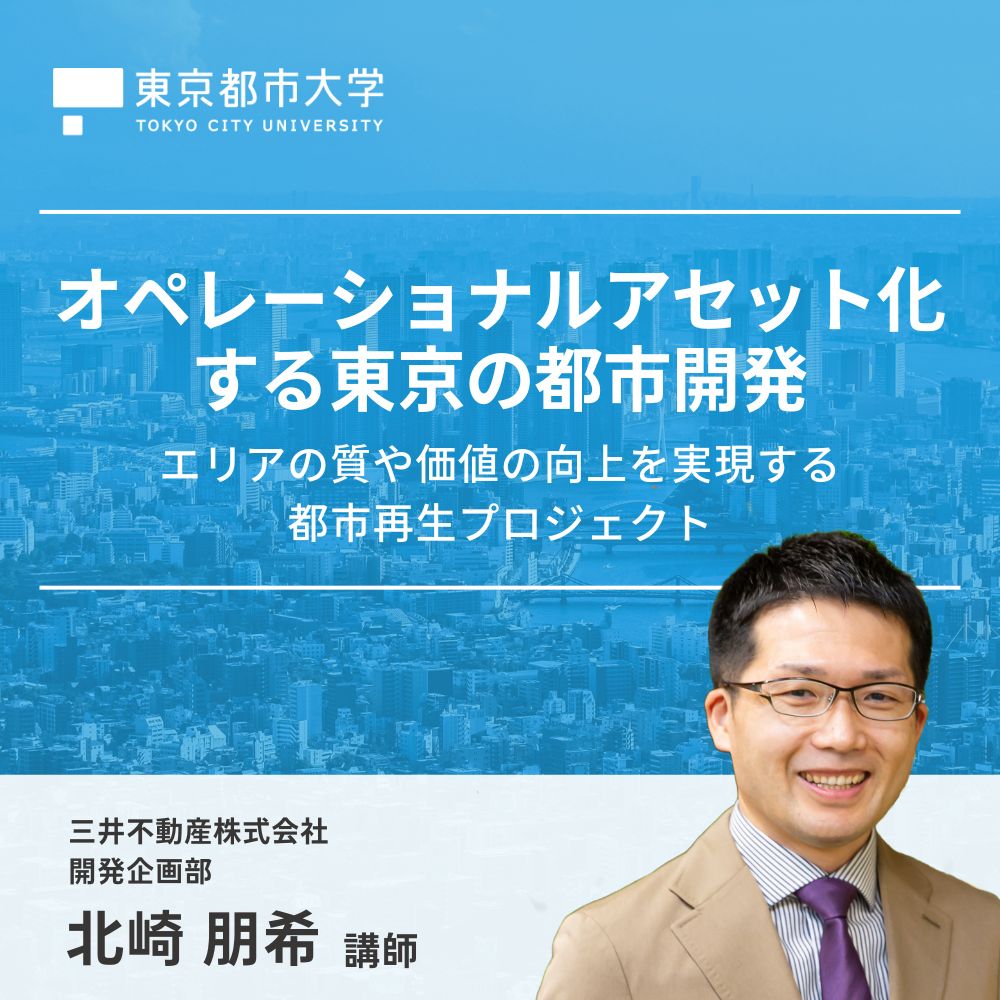
講義 オペレーショナルアセット化する東京の都市開発 – エリアの質や価値の向上を実現する都市再生プロジェクト
講師名 北崎朋希 講義概要
これまでの都市開発は、立地によって安定的な収益が見込める手堅いビジネスであった。
しかし近年では、劇場、美術館、インキュベーション施設など多様な用途を導入し、エリアの魅力を高めることで立地ポテンシャルを飛躍させ、収益性を向上させる事例が増加している。
こうした開発は、大丸有、日本橋、渋谷、六本木などで先行的に進められ、虎ノ門、新宿、池袋、品川、新橋などにも広がりつつある。
その背景には、各地域のアンカープレイヤーとなる不動産会社や鉄道会社の戦略的な関与があり、東京は世界でも類を見ない民間主導による地域間競争の舞台となっている。
本講義では、こうした都市開発の動向や仕組み、それを支えるプレイヤーの役割について具体的事例を通じて報告・考察する。講師紹介

所属 三井不動産株式会社開発企画部
経歴 2006年に(株)野村総合研究所入社。
都市政策や不動産開発・投資に関する調査研究やコンサルティングに従事。
内閣官房地域活性化統合事務局都市再生の推進に係る有識者ボード経済効果WG委員、内閣府地域再生エリアマネジメント負担金制度有識者会議委員などを務める。
2015年から2017年まで三井不動産アメリカ(株)で不動産開発・投資に関する調査研究に従事。
2018年から三井不動産(株)において国内外の都市政策や不動産開発・投資に関する調査に携わる。
近著に「東京・都市再生の真実-ガラパゴス化する不動産開発の最前線-」(水曜社、単著、日本不動産学会著作賞受賞)、「協働型都市開発-国際比較による新たな潮流と展望-」(近代科学社、共著、日本都市計画学会論文賞受賞)(不動産テック-巨大産業の破壊者たち-」(日経BP社、共著)などがある。
筑波大学システム情報系社会工学域非常勤講師。 -
都市空間DXに向けたAIデータ活用戦略
谷山智彦
-
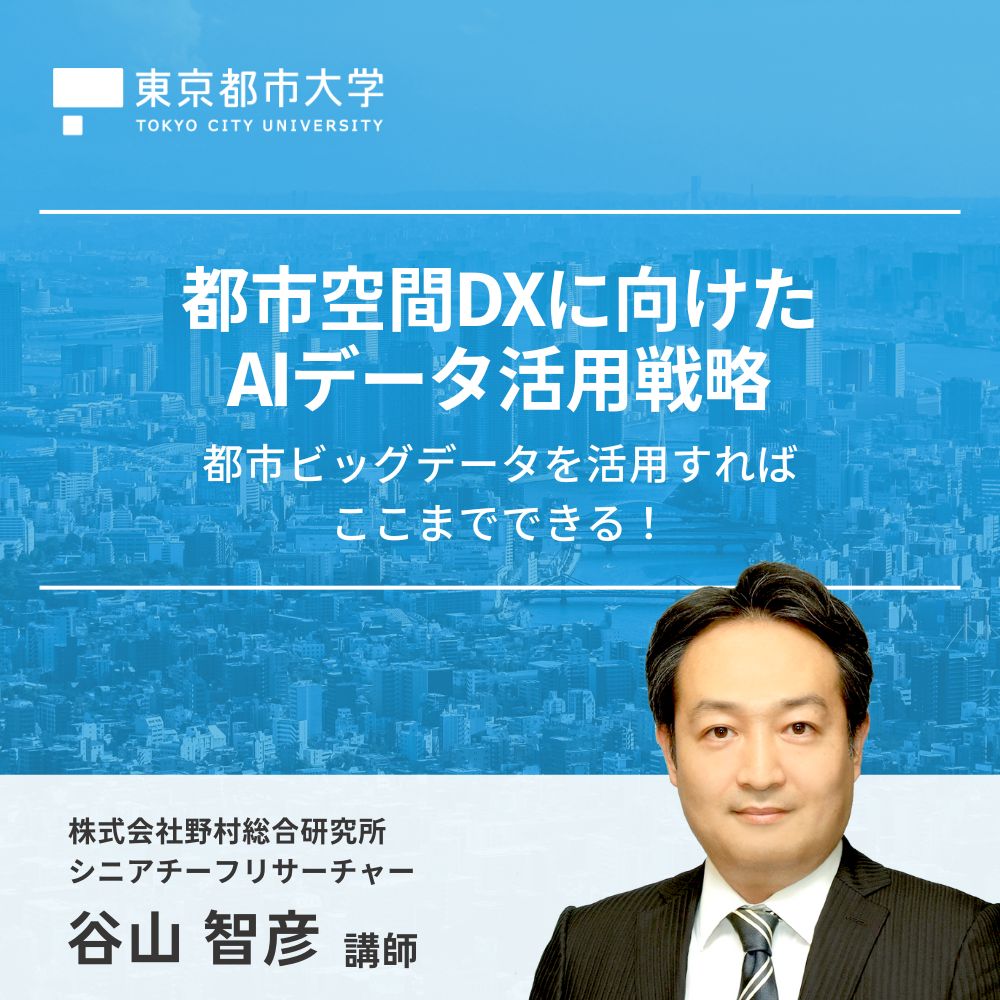
講義 都市空間DXに向けたAIデータ活用戦略 – 都市ビッグデータを活用すればここまでできる!
講師名 谷山智彦 事前準備 PC
講義概要
都市空間はデータの宝庫です。
本講義では、不動産、交通、環境、人流等、都市空間から日々生み出される多種多様なビッグデータに基づき、人工知能(AI)等の最先端の技術を用いてどのような分析ができるのかを学びます。
ここでは単なるデータ分析に留まらず、そこから都市空間のDXを目指して、どのような革新的なビジネスやサービスが創造できるのかを議論します。
具体的には、DXの基本的な考え方から都市空間におけるデータ活用の実例、そしてAIやアナリティクスを用いたサービス開発の応用までを、実際の事例とともに学びます。
講義を通じて、参加者が都市データを活用し、新たなビジネスやサービスを創造する視点と実践的な知見を養うことを目指します。講師紹介

所属 株式会社野村総合研究所
役職 シニアチーフリサーチャー
経歴 2002年慶應義塾大学総合政策学部卒業。
2004年同大学大学院政策・メディア研究科修士課程修了。
2010年大阪大学大学院経済学研究科博士課程修了。博士(経済学)。
2004年に株式会社野村総合研究所(NRI)に入社後、主に不動産分野に関する調査研究及びコンサルティング業務に従事。
2017年11月よりケネディクス株式会社とNRIとの合弁会社であるビットリアルティ株式会社の取締役に就任し、2020年3月より同社取締役副社長として不動産分野におけるデジタル戦略を推進。
2023年4月よりNRI未来創発センターに所属し、デジタル都市インフラ研究室長等を経て、2025年4月より現職。
主な専門分野は、不動産等に関わるファイナンス理論、データサイエンス、デジタル戦略等。また、国土審議会企画部会専門委員、日本不動産金融工学学会(JAREFE)副会長、早稲田大学ビジネススクール非常勤講師等を務める。 -
都市・不動産とサスティナブルファイナンス
堀江隆一
-

講義 都市・不動産とサスティナブルファイナンス - ESG投資は都市・不動産にどのような影響を与えるのか
講師名 堀江隆一 講義概要
「サステナブルファイナンス」、「ESG投資」は、都市・不動産のサステナビリティを推進するためのキーワードの一つとなる。
最初に、機関投資家や金融機関が進めてきたESG投資の潮流につき、国内外の政府や国際イニシアティブの動向と共に説明し、次いで不動産・まちづくりにおけるESG投資とは具体的にどのようなものか、様々な手法から国内外の具体的事例まで、グリーンビル認証制度を含めて解説する。
最後に、ESG投資の発展形としてのインパクト投資を紹介し、社会的インパクトの創出と都市・不動産の経済的価値の向上について論じる。参加者が主体的に学べるように、講義の中にグループディスカッションを取り入れる。講師紹介

所属 CSRデザイン環境投資顧問株式会社
役職 代表取締役社長
経歴 2010年にCSRデザイン環境投資顧問株式会社を共同で設立し、不動産・インフラ投資運用へのESG組込みに係る支援業務や、環境不動産・サステナブルファイナンスに関する公的な調査業務を行う。
当社設立前は、日本興業銀行、メリルリンチ証券、ドイツ証券に合計20年以上勤務。
東京大学法学部卒、カリフォルニア大学バークレー校MBA。
国土交通省「ESG投資の普及促進に向けた勉強会」座長、環境省「グリーン投資促進のための市場創出・活性化検討会」委員、「国連環境計画金融イニシアティブ(UNEP FI)」不動産WG特別顧問などを歴任。
現在は国交省・経産省・環境省等の多くの検討会の委員、「21世紀金融行動原則」不動産WG共同座長、「責任投資原則(PRI)」不動産アドバイザリーコミティ委員、GRESBリアルエステイト スタンダードコミティ委員など。 -
サスティナブルな都市モビリティ
西山敏樹
-
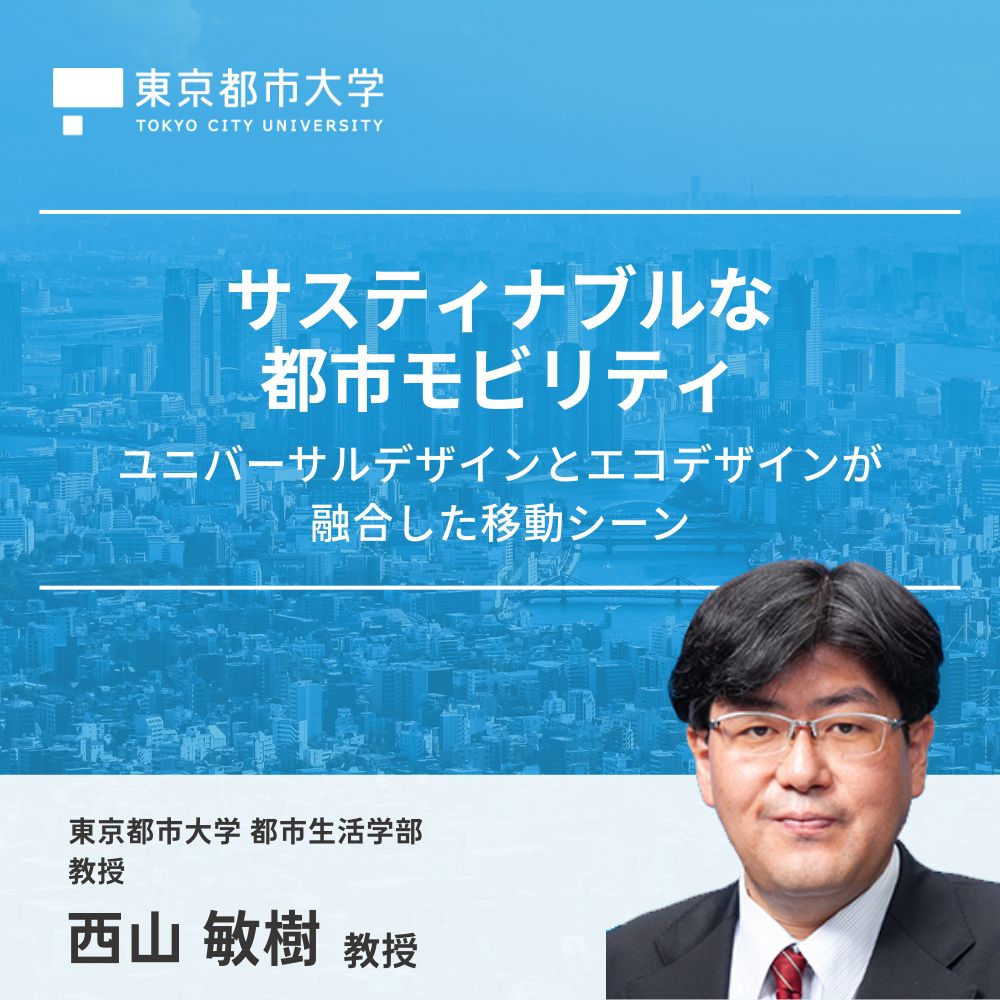
講義 サスティナブルな都市モビリティ - ユニバーサルデザインとエコデザインが融合した移動シーン
講師名 西山敏樹 事前準備 受講生が用意するものは特にありませんが,以下の担当者の著作は講義の理解を進めます。 西山敏樹「近未来の交通・物流と都市生活~ユニバーサルデザインとエコデザインの融合」(慶應義塾大学出版会・2016)
講義概要
なぜ人は移動をするのか?
それは、物・情報・場という三大欲求を満たしていくために必要なことだからだ。
日本の都市生活の移動シーンでは、高齢者や障がい者の増加、子どもとその親、外国人の存在が、いまだ十分に考慮されているとは言い難い状況である。まさしくユニバーサルデザイン化が必要である。
そして、持続可能性を考慮する観点で交通事業にはエコデザイン化も社会的に要請されている。
このユニバーサルデザインとエコデザインが融合した未来の都市モビリティシーンをどう描けば良いのか。
担当者の研究の実例も織り交ぜつつ、スペキュラティブデザインのアプローチで講義する。講師紹介

所属 東京都市大学 都市生活学部 及び 大学院環境情報学研究科都市生活学専攻
役職 教授
経歴 1976年東京生まれ。
慶應義塾大学総合政策学部社会経営コース卒業、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修士課程及び後期博士課程修了。
慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特任講師、慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科特任准教授、慶應義塾大学教養研究センター特任准教授、慶應義塾大学医学部特任准教授等を経て現職。
大学生協員外監事を兼務。
又、一般社団法人日本テレワーク学会理事、特定非営利活動法人ヒューマンインタフェース学会評議員、一般社団法人日本イノベーション融合学会前理事長ほか、学会の役職も多数歴任。
専門領域はユニバーサルデザイン・バリアフリー、モビリティデザイン、未来都市論、社会調査法等。交通用車輌の開発に関する大型プロジェクトを多数経験。
ユニバーサルデザインに関わる地域開発も多数手がけ、研究成果表彰も25件にのぼる。専門領域に関わる著書も30冊にのぼり、公共交通に関連するマスコミ出演も多数。 -
脱炭素社会構築に向けた経営戦略
菊池武晴
-

講義 脱炭素社会構築に向けた経営戦略 - 脱炭素社会におけるビジネスチャンスとリスクとは
講師名 菊池武晴 事前準備 PC
講義概要
先行き不透明な時代ながら、今後長期的に変わらない課題として、地球温暖化とその対応が挙げられる。
人間活動に伴うCO2排出を実質ゼロにする脱炭素社会構築のためには、企業、行政による強いリーダーシップが求められている。
この対応は、グリーントランスフォーメーション(GX)と称せられ、社会全体の変革が必要とされている。
本講義では、GX推進法など関連政策や脱炭素にかかる技術動向、サスティナブル経営の先進企業の動向等を概観し、今後求められる経営戦略や都市政策について皆さんと考える機会にしたい。講師紹介

所属 東京都市大学 都市生活学部
役職 教授
経歴 1995年 日本開発銀行(現㈱日本政策投資銀行)入行。
情報通信業、物流業、エネルギー業への融資担当、企業への環境格付評価担当等を経て、2011年 環境・CSR部課長。
2012年 環境省出向。
2013年 一般社団法人グリーンファイナンス推進機構(現㈱脱炭素化支援機構)事業部長。
2016年 一般財団法人日本経済研究所イノベーション創造センター長。
2022年 福井工業大学経営情報学部教授。
2025年4月より現職。
研究テーマは、サスティナブル経営、再生可能エネルギーの地域経済活性化効果、地域公共交通問題。神戸大学大学院経済学研究科博士後期課程修了、博士(経済学)。 -
サスティナブルな都市とエリアマネジメント
坂井 文
-

講義 サスティナブルな都市とエリアマネジメント - 都市の価値を上げるためのエリアマネジメントのあり方とは
講師名 坂井 文 事前準備 PC
講義概要
少子高齢社会の日本においては、都市の新たなマネジメントの手法が模索され、都市のコンパクト化もすすめられている。
成熟した社会に対応して、これまでの社会資本の整備を中心とした都市計画から、社会関係資本の構築をすすめるエリアマネジメントの重要性が高まっており、国内の大都市・地方都市の中心部や住宅市街地において展開されている。
複数の事例を通してエリアマネジメントを理解し、海外の先進事例から知見を得ながら、今後の展開に向けて議論する。講師紹介

所属 東京都市大学 都市生活学部
役職 教授
経歴 横浜国立大学工学部建築学科卒業後、JR東日本勤務。
ハーバード大学ランドスケープ修士修了後、ササキ・アソシエイツ(ボストン)勤務。
北海道大学大学院工学研究科建築学専攻准教授を経て、現職。
ロンドン大学PhD。一級建築士。専門は建築・都市計画。
内閣府、国土交通省社会資本整備審議会、文化庁文化審議会等や、東京都特別区等の自治体の都市計画、景観、公園等の審議会、検討会等の委員を務める。
学術会議連携会員。
日本都市計画学会、日本建築学会の理事歴任。書籍 『イギリスとアメリカの公共空間マネジメント(鹿島出版会)』『英国CABEと建築デザイン・都市景観(学芸出版社)』など。